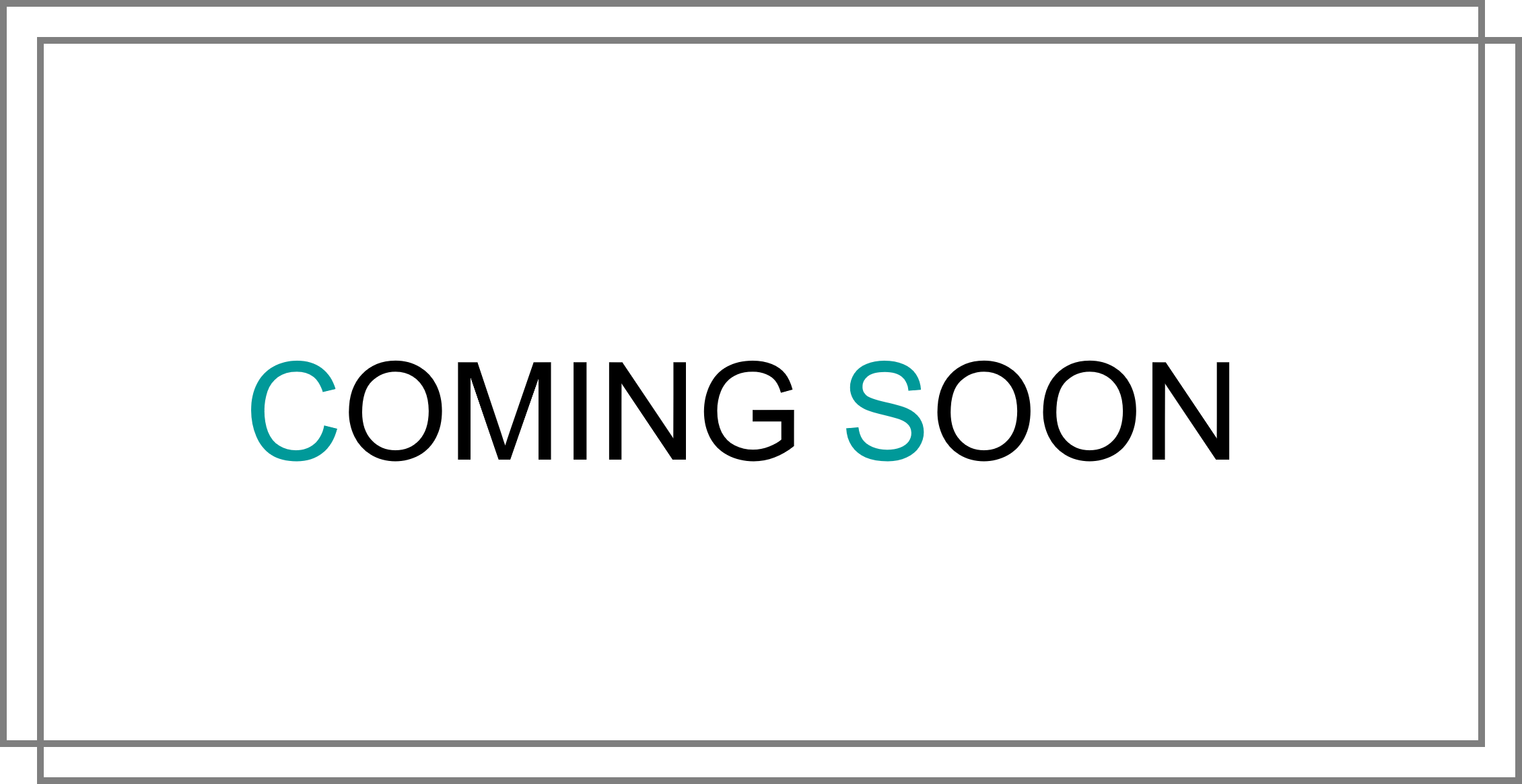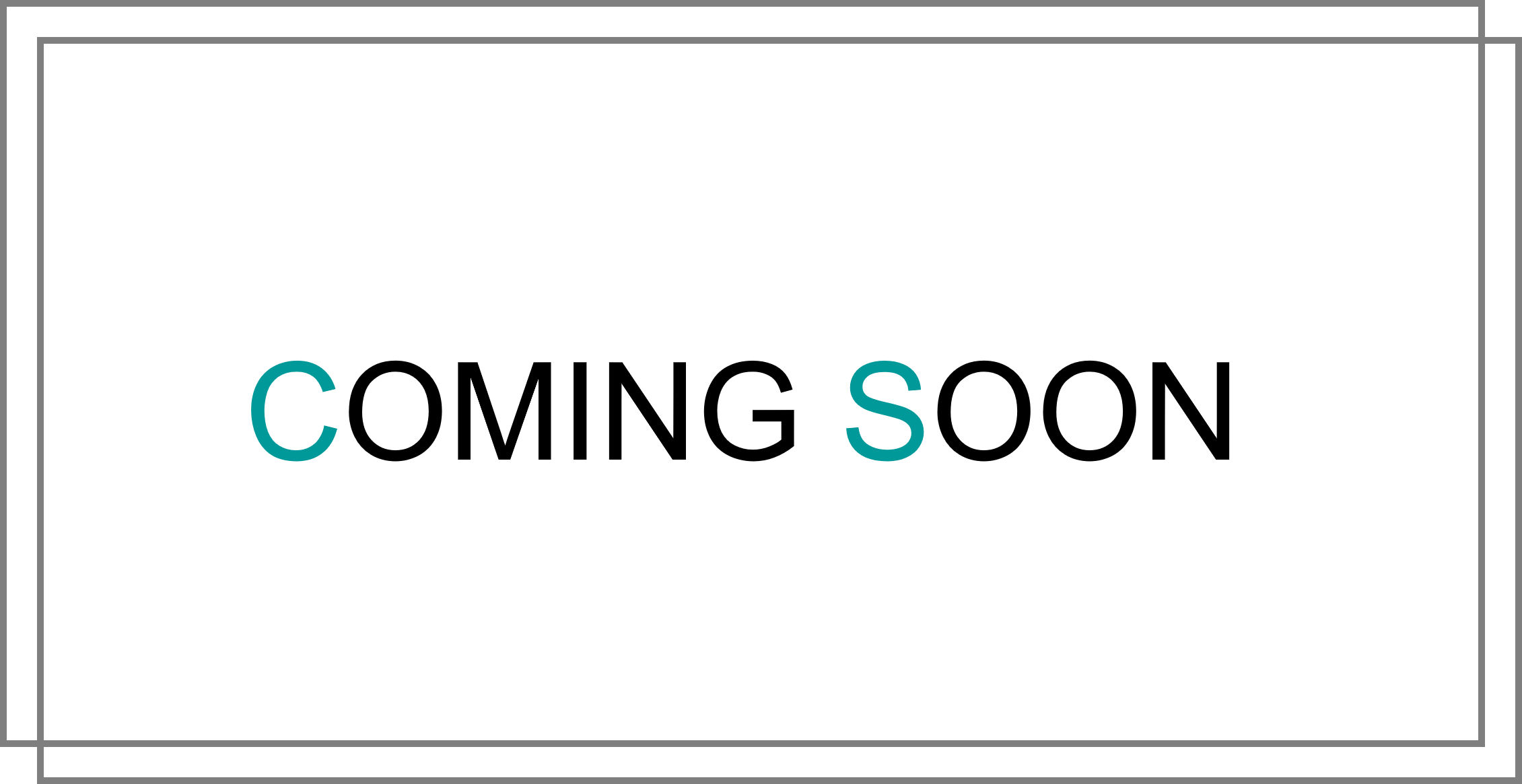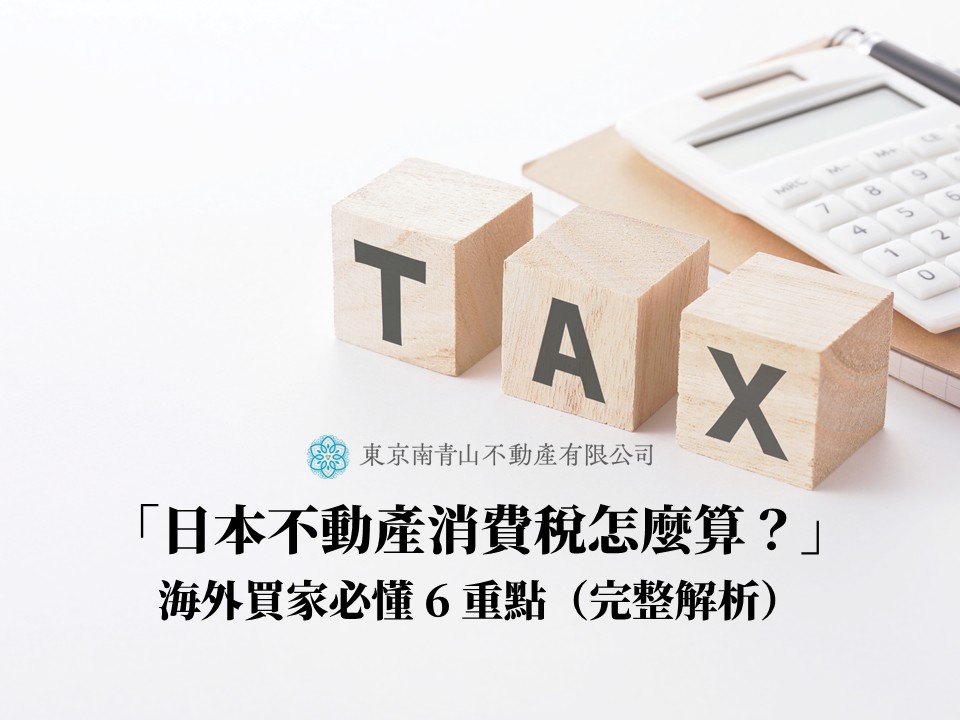宮城県の南端、蔵王連峰を望む白石市。
豊かな自然と清らかな水に恵まれたこの地では、古くから手漉きの和紙づくりが行われてきました。
その名も「白石和紙(しろいしわし)」。一枚の紙に込められているのは、職人たちの丹念な手仕事と、四季のうつろいを感じながら生きてきた人々の知恵です。
古くから伝わる「みちのくの紙」
東北地方では、平安時代にはすでに「陸奥紙(みちのくがみ)」と呼ばれる和紙が都へ献上されていたといわれています。
『源氏物語』や『枕草子』の中にも、陸奥の紙を「ふくよかで美しい」とたたえる表現が見られます。
白石もまた、その伝統の流れをくむ土地でした。
白石和紙が本格的に発展したのは江戸時代。仙台藩主・伊達政宗が産業を奨励し、楮(こうぞ)などの紙の原料を育てることを勧めたことがきっかけとされています。
冬の間、農作業の手が空く農家が副業として紙を漉くようになり、やがて白石は「紙の里」として知られるようになりました。
最盛期には、およそ60種類もの紙が漉かれていたと伝えられています。奉書紙や厚紙、ちり紙、障子紙など、暮らしの中で使われるさまざまな紙が、白石の職人たちの手から生まれていきました。
宮城 白石城
格子影と障子に囲まれた和紙ポスター枠
自然が育てる紙のぬくもり
白石和紙の主な原料は楮(こうぞ)です。中でも「トラフコウゾ」と呼ばれる品種は、繊維が細く長く、強度に優れていることで知られています。繊維が長いことで、薄く漉いても破れにくく、また繊維同士が絡み合うことで、軽さと柔軟性、耐久性を同時に兼ね備えた紙が生まれます。さらに、繊維の細かさが紙の表面の滑らかさや光沢、温かみを生むため、手に取った瞬間に感じる感触が独特です。
冬、刈り取った楮は蒸して皮をむき、外側の黒い部分を削ぎ落とすと、白く柔らかな繊維が現れます。水にさらして汚れを取り、木槌で叩いて繊維をほぐす工程は、紙の強度としなやかさを決定づける重要な作業です。この段階で繊維が均一にほぐされることで、のちに紙漉きの際にムラなく美しい紙面が生まれます。
原料の準備から紙を漉くまで、すべてが手仕事です。職人は簀桁(すげた)という竹のすのこ状の道具を用い、水槽の中で前後にゆらしながら繊維を均等にすくい上げます。
何度も何度もすくって層を重ねることで、厚みや強度を微妙に調整し、透け感や柔らかさの加減もコントロールします。こうして漉き上げられた紙は、一枚一枚、職人の感覚や気候、水温の影響を受けて表情が変わるのです。
水を切った紙を板に貼って天日に干すと、乾燥するにつれて繊維が自然に絡まり、しっとりとした光沢と温かみのある手触りが生まれます。
光にかざすと、薄く漉かれた紙の中で繊維の微細な揺らぎや空気の層が光を柔らかく反射し、まるで生きているかのような質感を感じさせます。
とても手間と時間のかかる作業ですが、その分だけ一枚一枚に独特の表情と生命感が宿ります。白石和紙のやさしい風合いは、この土地の清らかな水と冬の寒さ、そして職人の手の温度と熟練の技が生み出しているのです。
白石和紙の魅力「紙布」と「紙子」
白石和紙の特徴は、その用途の広さにもあります。
江戸時代、綿の取れにくい東北地方では、紙を布の代わりに使う知恵が生まれました。
和紙を細く切って糸のように撚り、織り上げる「紙布(しふ)」、また、こんにゃく糊を塗って強度と防水性を高めた「紙子(かみこ)」です。
軽くてあたたかく、丈夫な紙子は、庶民の冬の衣として重宝されました。
また、白石で作られた紙布は、そのしなやかさと美しさから「紙の織物」としても知られています。
こうした技術は、現代にも受け継がれています。
たとえば奈良・東大寺の「お水取り(修二会)」で、僧侶が身につける紙衣の素材として、白石和紙が使われているのです。
千年以上続く法要に、遠く白石の紙が息づいている。
それは和紙を作る職人たちにとっても大きな誇りです。
一度は途絶え、職人の情熱によって復活へ
明治時代に入り、洋紙が大量生産されるようになると、全国の手漉き和紙産業は次第に衰えていきました。
白石でも例外ではなく、昭和初期には紙漉きを続ける家がわずか数軒にまで減ってしまいます。
そんな中で、白石和紙を絶やすまいと立ち上がったのが、地元の紙漉き職人・遠藤忠雄さんでした。
伝統の技を受け継ぎながら、こんにゃく糊を使った紙布や、模様を浮かび上がらせる拓本染めなど、新しい試みを重ねていきました。
その情熱が、戦後の白石和紙の復興につながっていきます。
昭和23(1948)年ごろには、こんにゃく粉を溶いた糊を塗って強化した和紙に型板で模様をつける“拓本染め”が生み出されました。
さらに昭和57(1982)年には「宮城県伝統的工芸品」に指定され、白石和紙は地域を代表する手仕事として再び脚光を浴びるようになりました。近年では、地元の有志グループを中心に、和紙の展示やワークショップを通じて、その魅力を伝えています。
【現代に生きる和紙のかたち】
現代の白石和紙は、伝統的な書画用紙や障子紙だけでなく、日常のさまざまな場面で新しい命を吹き込まれています。名刺入れや財布、ランプシェードなど、和紙ならではの質感を活かした工芸品も人気です。
特に人気なのが「和紙あかり」。やわらかな光を透かす和紙のランプは、どこか懐かしく、心をほっとさせてくれます。その光の中に、職人の手仕事と白石の自然の気配がそっと息づいているようです。
また、デザイナーやアーティストとのコラボレーションも進み、和紙の新しい可能性が広がっています。
障子紙
和紙あかり
【白石三大特産のひとつとして】
白石には、古くから「白石温麺(うーめん)」「白石葛」「白石和紙」という三つの特産品があります。いずれも自然の恵みと人の手から生まれたものです。なかでも白石和紙は、「書く」「包む」「着る」「照らす」と、多様な形で人々の生活に寄り添ってきました。
手に触れると、ざらりとした独特の感触の奥に、ぬくもりのようなものを感じます。それは、紙そのものに土地の風や水、そして職人の息づかいが染み込んでいるからかもしれません。
「一枚として同じ紙はない」。それが手漉き和紙の最大の魅力です。白石の職人たちは、この個性あふれる紙づくりの技を代々受け継いできました。
清少納言や紫式部も愛用し、松尾芭蕉が身にまとったとも伝えられる白石和紙。時代ごとに用途を変えながら受け継がれてきたその存在は、今も静かに息づいています。古くから受け継がれるその世界に、思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。