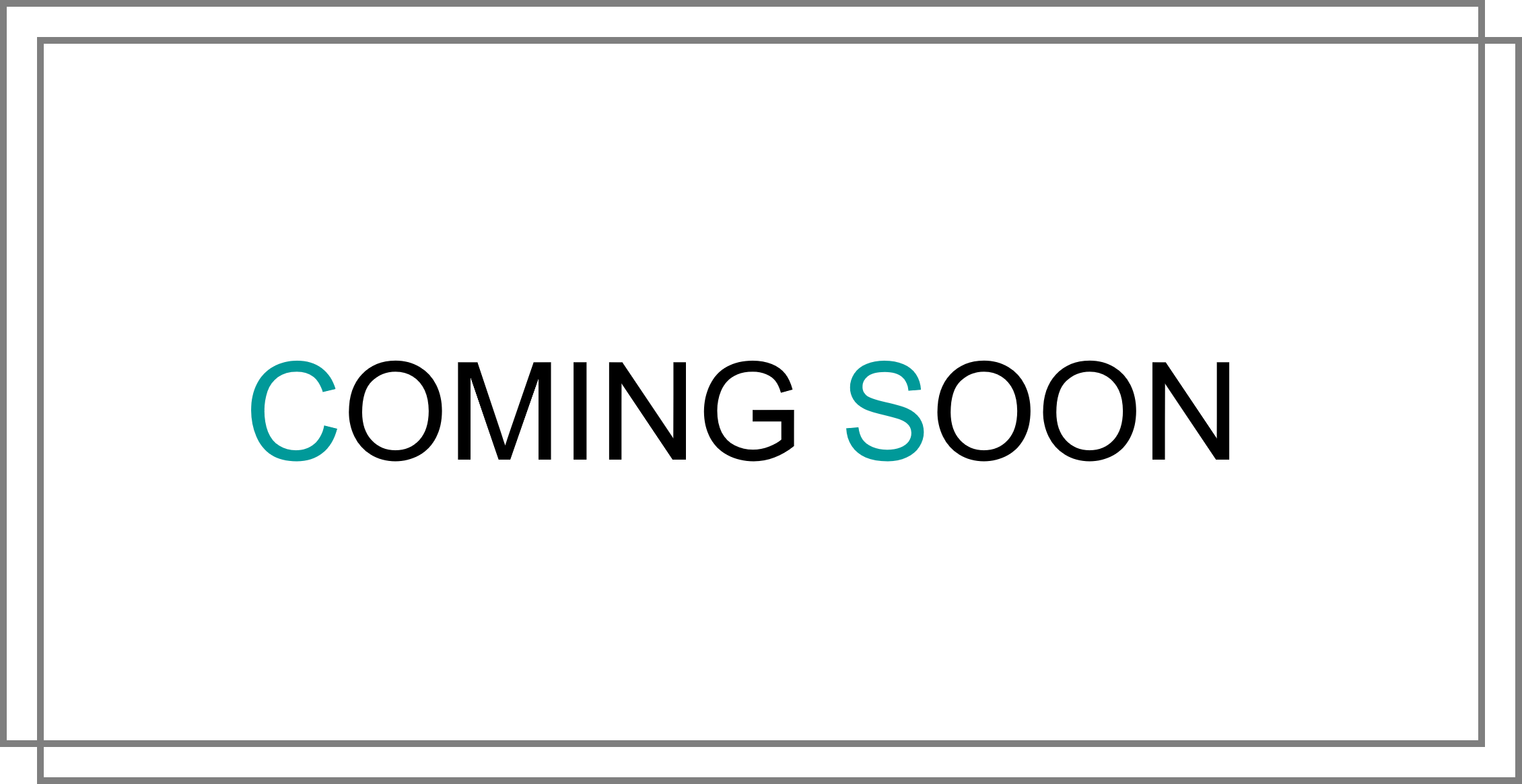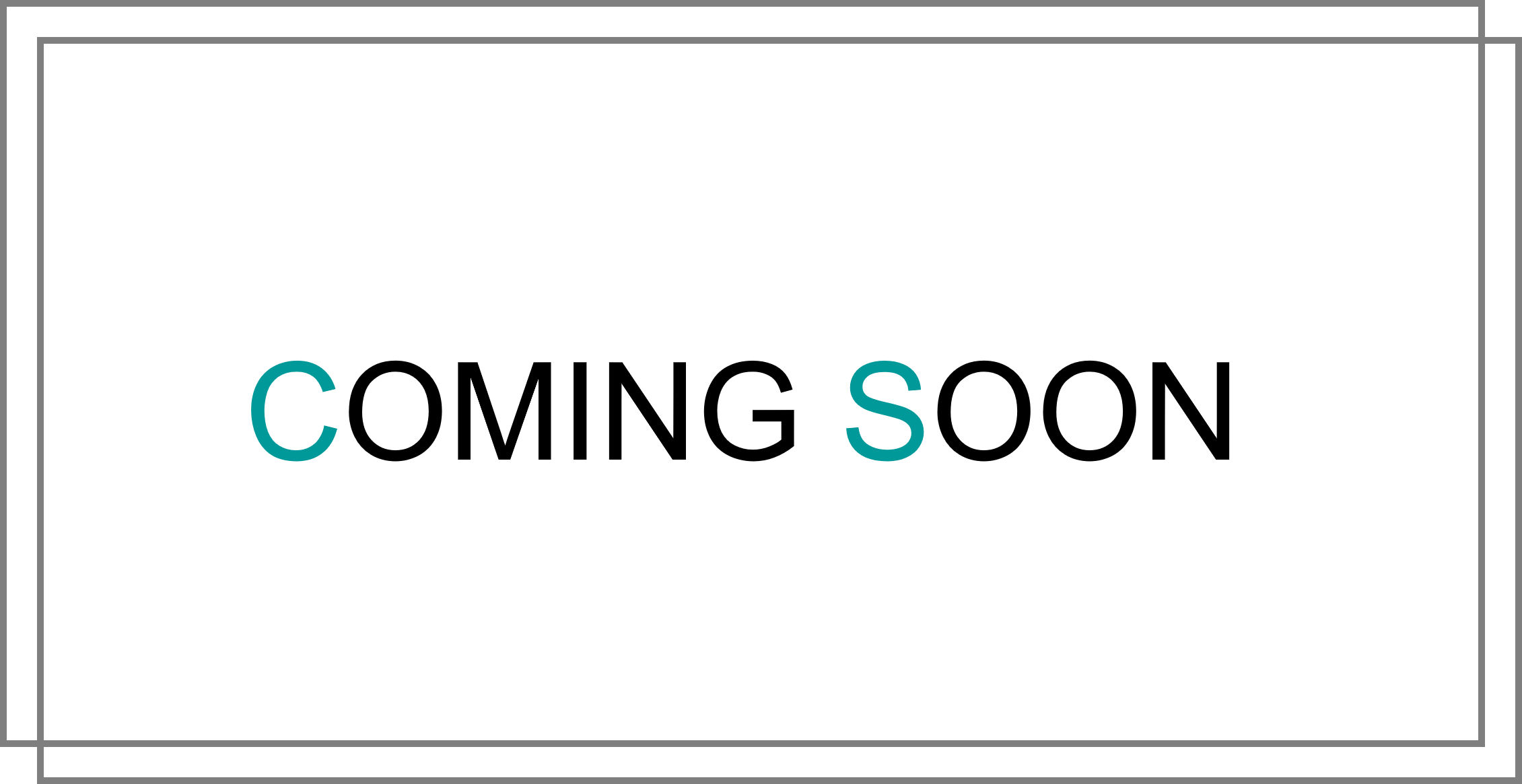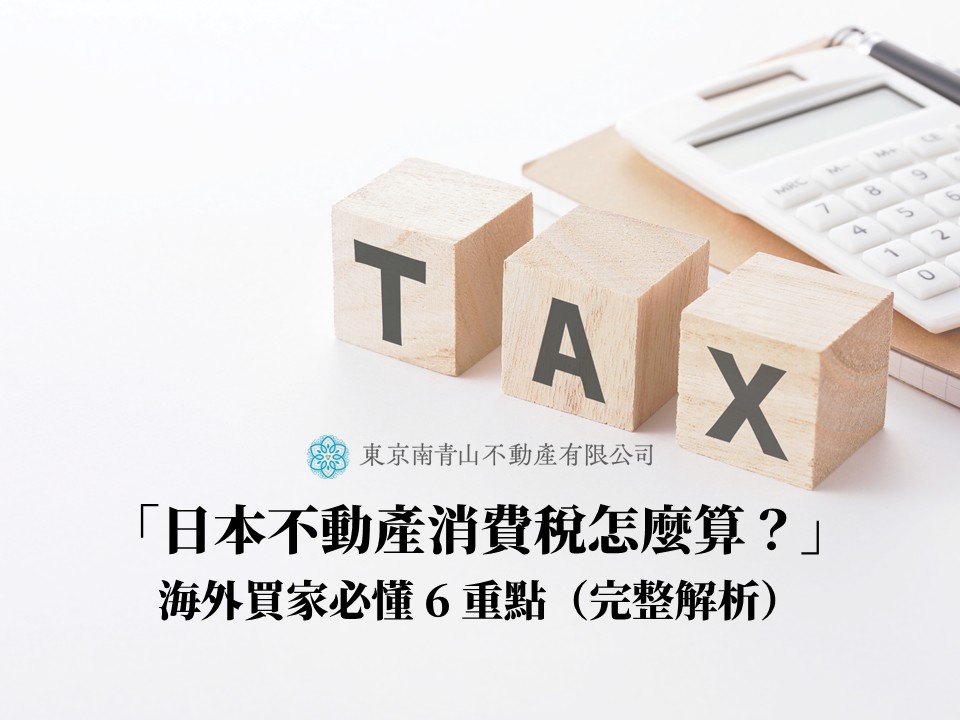江戸時代に誕生し、約400年に渡り受け継がれている「南部鉄器」。現在も岩手県盛岡市、奥州市では、おなじみの鉄瓶をはじめ、鍋やスキレット、鍋敷きなどさまざまな製品がつくられています。今回は、鉄瓶を中心に南部鉄器の魅力やお手入れ方法、豆知識についてご紹介します。

水や料理が美味しくなる!?南部鉄瓶のメリット&豆知識
●水がまろやかに、おいしくなる
一般的に、南部鉄瓶で沸かした湯は、口当たりがまろやかになるといわれています。これは、鉄が水のカルキを吸着するため。鉄瓶に水を入れて火にかけ、沸騰したら蓋を外し、弱火で10分ほど沸かし続けるのがポイントです。
日常的に南部鉄瓶を利用している人からは、白湯をはじめ、コーヒーや紅茶、インスタントスープなどもおいしくなるという声も。また、鍋は具だくさんの汁物や煮込み料理にぴったりです。
●鉄分補給を助けてくれる
多くの場合、南部鉄器は内側にコーティングを施していません。そのため、南部鉄瓶で沸かした湯には鉄から溶けだした鉄分が含まれていることもよく知られています。この溶けだした鉄分は、体に吸収されやすい二価鉄(ヘム鉄)であることがわかっており、不足しがちな鉄分の補給や貧血予防などの効果が期待できます。
●保温効果が高い
南部鉄器は厚みがあるため、一度熱すると冷めにくいという特徴も。調理中に温度のムラが出にくい点も魅力です。
●鉄瓶には表・裏がある
南部鉄瓶は注ぎ口が右に見える面を「表」、反対側を「裏」としています。これは、おもてなしの際に鉄瓶のつるを右手で持って注ぐことを想定した場合、客人から鑑賞される面を「表」としているからです。
●お湯が沸く際の「音」にも個性がある
南部鉄器製の風鈴は高く澄んだ音がするとして人気がありますが、鉄瓶でお湯が沸く際の音が一つひとつ違うのはご存知でしょうか。
聴き比べる機会はないかもしれませんが、ステンレス製のやかんや電気ポットとはひと味違った音が楽しめます。ぜひ南部鉄瓶で湯を沸かす際には耳を傾けてみてください。
南部鉄瓶のお手入れ方法
いつかは欲しい南部鉄瓶。憧れる一方で、安いものではないため「使いこなせるか自信がない」と不安の声も。そこで、自宅で簡単にできるお手入れ方法をご紹介します。
●購入後はまず「ならし」から
本体を水で軽くすすぎ、8分目まで水を入れて中火にかけます。沸騰したらお湯を捨て、これを2~3回繰り返します。「ならし」作業を行うことで、水に含まれるカルシウムやマグネシウムが結晶化し、鉄瓶内部に白い膜のような形状で付着します。これを「湯垢(ゆあか)」といい、錆つきを防ぎます。
鉄鍋やスキレットの場合は、軽く洗って水分を飛ばしてから油を塗って空焼きし、全体に油をなじませる「シーズニング」の作業が必要となります。
●基本的なお手入れ方法は「濡れたまま放置しない」
南部鉄瓶は内側にコーティングがされていないため、長時間お湯を入れたままにしておくと、錆や湯が濁る原因に。使用後は必ず、鉄瓶内を空っぽにし、ふたを外して予熱で乾かすか、軽く空焚きをして完全に乾燥させましょう。
ただし、必要以上に熱すると破損の原因になります。30秒ほど熱した後は、余熱を利用して乾燥させましょう。
●たわしなどでこすらない
基本的に、鉄瓶の内部には手を触れないこと。湯垢を落としてしまうため、鉄瓶の内部はたわしやスポンジでこするのは厳禁です。外部は乾いた布巾で拭く程度にとどめます。
●錆びついたり、お湯が濁ってきたら「煎茶を煮出す」
鉄瓶の内部が赤く錆びついて沸かしたお湯が濁っていたり、鉄っぽいにおいがある場合は、毎日飲んでいるお茶が活躍。
本体をすすいで8分目くらいまで水を入れ、茶さじ1杯程度の煎茶をだしパックなどに入れたものと一緒に30分ほど煮だします。煎茶に含まれるタンニンと鉄分の化学反応を利用した技法で、お茶を煮出した後は湯にやや色がつくことがありますが、濁りやにおいがなくなったら普段通り使用できます。
ちなみに、錆そのものにはほとんど害はなく、お湯を沸かしても濁らなければそのまま使うことができます。錆を落とそうとしてたわしでこすると、かえって錆がひどくなるため要注意。
●長持ちさせる秘訣は「毎日使う」
しまい込んでしまうと錆びなどの原因になります。
使い続けることで湯垢がさらに付着するため、やかんやポットのように、お湯を沸かすための生活用品として毎日活用するのがおすすめ。
どうしても長期間収納する場合は、風通しのいい場所に保管します。
(まとめ)
南部鉄器の中でも、とくに一般的な「南部鉄瓶」のお手入れ方法についてご紹介しました。一つひとつ職人の手で作られている南部鉄瓶は、ほとんどの場合、修理が可能です。
錆びついてしまってどうしても落ちないなど、お困りの際は製造元に相談してみてください。