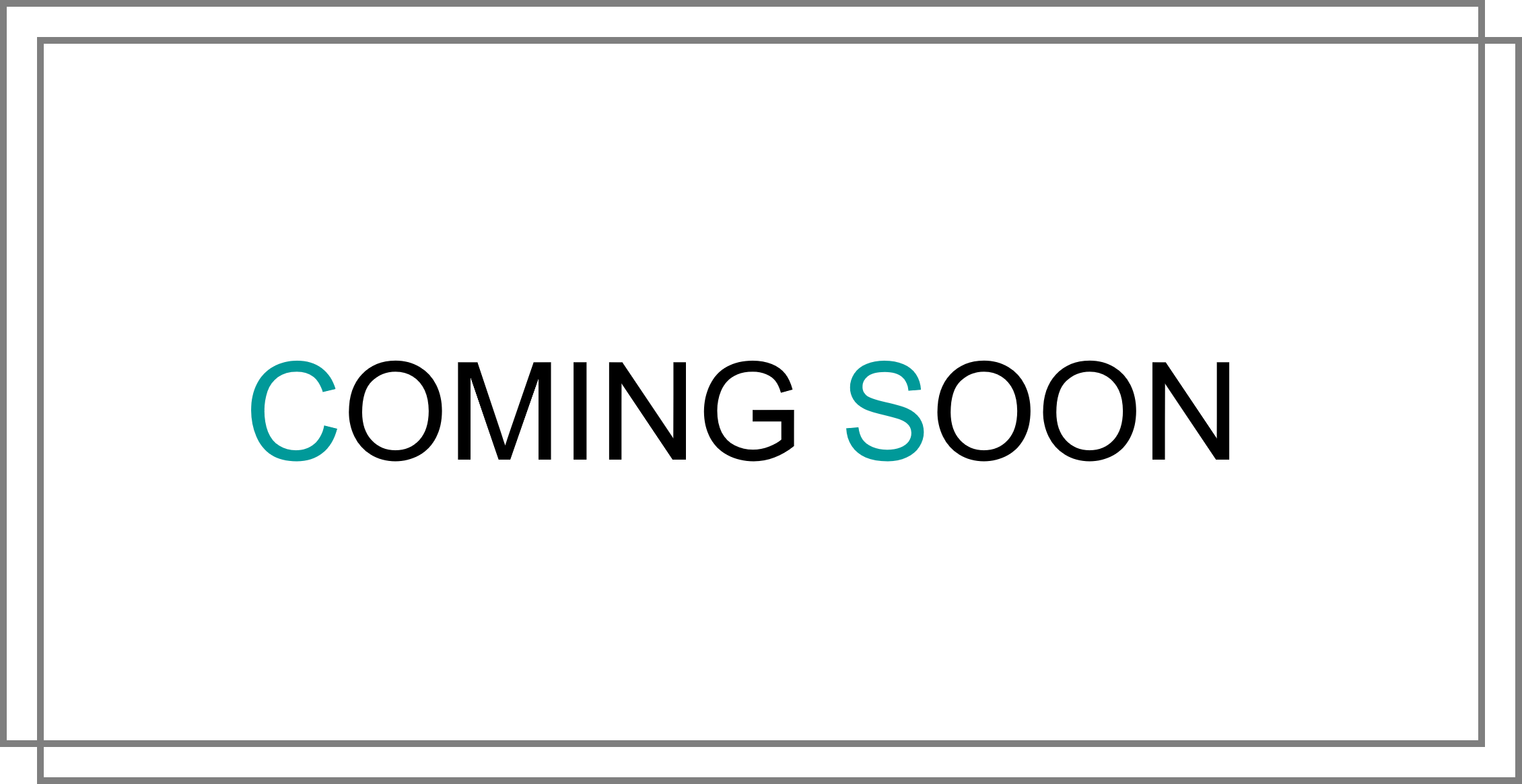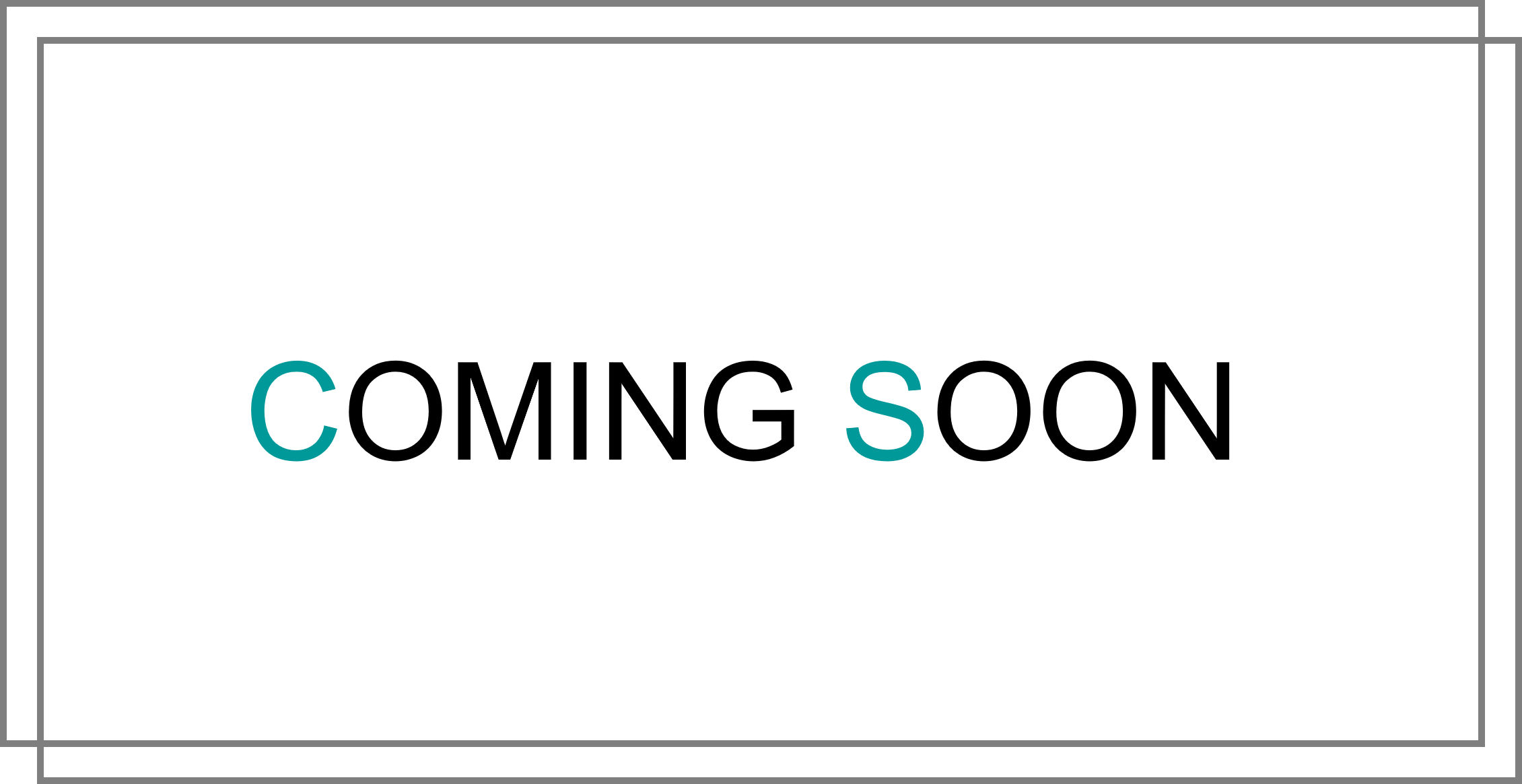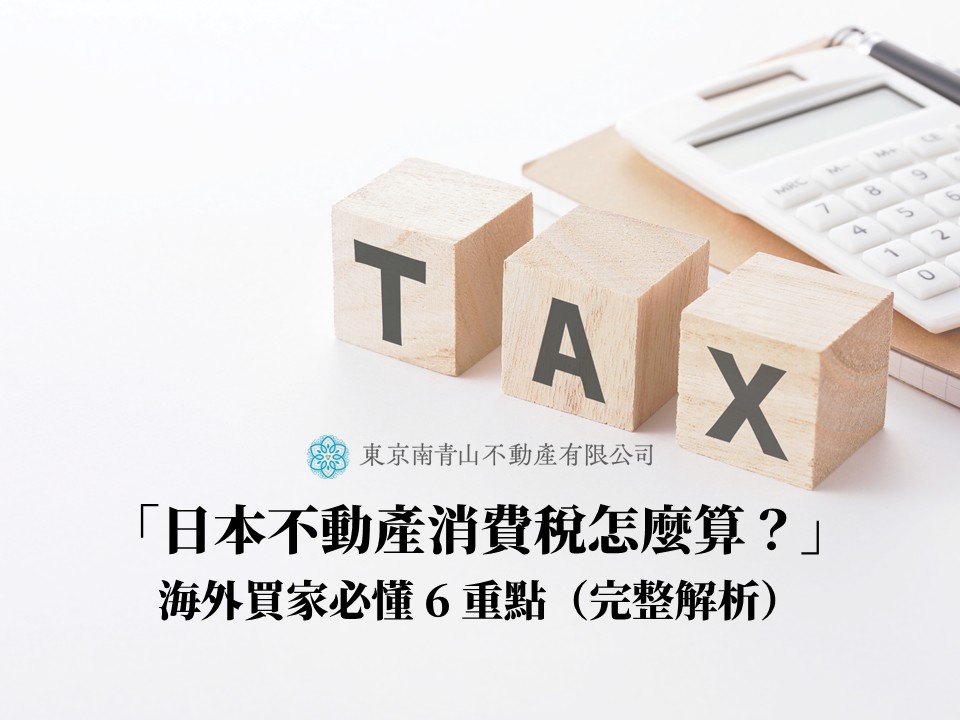約700年前の室町時代に成立し、現代に受け継がれる「いけばな」の文化。現代では数多くの流派が存在し、300以上あるともいわれています。今回は、三大流派とされる「池坊(いけのぼう)」、「小原流(おはらりゅう)」、「草月流(そうげつりゅう)」を中心に、いけばなの流派についてご紹介します。
いけばなの源流。伝統的な手法に加え、現代的ないけばなも手がける「池坊」
最古の流派であり、日本のいけばなの源流とされる「池坊」。京都・六角堂の僧侶、池坊専慶(いけのぼう・せんけい)が確立した「立花(りっか)」が現在のいけばなのルーツだと考えられています。そのため、“流”はつけず「池坊」と称するのが一般的です。江戸時代には形式美を重んじる「生花(しょうか)」が誕生し、戦後は「自由花(じゆうか)」が定着。伝統的な美感によるルールが設けられた「立花」、「生花」と比べ、「自由花」は文字通り自由で、幅広い表現ができます。
池坊の理念は、四季折々の草花の美しさをありのままに生かすこと。美しく咲く花や若葉だけでなく、色褪せた花、虫食い葉、枯れた葉や枝などもすべて同じ草木の命としてとらえ、美を見出しています。時代に合わせて変化をしながらも、今なお伝統的ないけばなの世界を伝承しています。
自由でダイナミックな表現が特徴「草月流」
1927年、勅使河原蒼風(てしがわら・そうふう)によって創設された「草月流」は、他の流派と比べて自由度が高いのが大きな特徴です。華道家を父に持つ蒼風は幼い頃からいけばなの指導を受けていましたが、従来の形式ばったスタイルに疑問を抱くようになり、草月流を確立します。
“型”や伝統にとらわれることなく、「いつでも、どこでも、だれにでも、そして、どのような素材を使ってもいけられる」を理念に掲げ、芸術としてのいけばなを追求し、戦後の前衛芸術運動にも影響を与えました。モダンな作品を多く手掛けており、現在は、家庭内の床の間といった狭小空間から、商業施設など大規模な空間まで、あらゆる空間を自由自在に彩ります。
現在、定番化したいけばなのスタイルを確立させた「小原流」
明治時代末期の1895年に創流された流派で、創始者は小原雲心(おはら・うんしん)。池坊でいけばなを学んだ雲心は、日本の西洋化が進むのに合わせ、洋間や洋風建築にも合ういけばなを目指すようになりました。
小原流は、口が広く浅い花器「水盤(すいばん)」に草木を「盛る」ように花を生ける「盛花(もりばな)」を確立。それまで他の流派が拒んできた洋花を積極的に取り入れるなど、当時のいけばな界ではかなり画期的な手法を生み出したことで知られています。現在、いけばなにおいて欠かせないとされる「剣山」を取り入れたのも、小原流が初めだといわれています。
さらに、2代目光雲(こううん)は男性中心だった指導者の職を女性にも開放し、いけばな文化の近代化に向けて尽力しました。
その他の主流な流派
◆龍生派(りゅうせいは)
明治19(1886)年に初代家元・吉村華芸(よしむら・かうん)が創流。社会全体が西洋化するに合わせ、自由度の高い様式が人気を集めていましたが、3代目華泉(かせん)は、植物自体を活かす古典的な考え方を再度提唱しました。
そこで現在は、伝統的な様式をふまえた「古典華」、一人一人の個性や感性を生かした「自由花」、さらに現代の住宅事情に合わせて誕生した縦横50センチ以下の寸法で表現する「ひびか」を展開。花を生ける人が自分自身の目で、手にした草木と向き合い、美しさを見出す「植物の貌(かお)」という考え方を大切にしています。
◆嵯峨御流(さがごりゅう)
平安時代、京都・大覚寺にて、嵯峨天皇が舟遊びの際に手折った菊を殿上の花瓶に挿したのが起源とされる流派で、関西を中心に全国に広がりました。
創設以来、受け継がれる「伝承花」、伝承花を発展させた新しい感覚の「化粧華」の大きく2つをもとに、さまざまな様式のいけばなを展開しています。
◆未生流(みしょうりゅう)
江戸時代中期に未生斎一甫(みしょうさい・いっぽ)と未生斎広甫(みしょうさい・こうほ)の2人の華道家によって創設されました。
未生流では、あるがままの自然を生かすのではなく、「人の手を介することで、さらなる本質的な美を表現する」ことを理念としています。
◆古流(こりゅう)
江戸時代中期に誕生した流派で、一志軒 今井宗普(いっしけん いまい・そうふ)が創設しました。西洋文化がもたらされた明治期に入ると一度衰退しますが、金沢で再興。儒教の考え方を表現し、江戸時代の伝統様式を受け継いでいます。
◆華道遠州(かどうえんしゅう)
江戸時代に活躍した茶人・小堀遠州(こぼり・えんしゅう)を流祖とする「華道遠州」。そのため、茶道とのかかわりが深く、「見立て」の美や、遠州が独自に見出した美意識「綺麗さび」を表現しています。
三大流派をはじめ、どの流派にも独自に築き上げた歴史や受け継がれる理念があり、同じ植物を使っても表現方法は大きく異なります。いけばなを習う際は、伝統的な技法を学びたいか、自由なスタイルを学びたいかに加え、自分の目で見て「素敵だな」と感じた作り手の流派を選ぶのもひとつの手です。いけばなのある暮らしを楽しんでみてはいかがでしょうか。