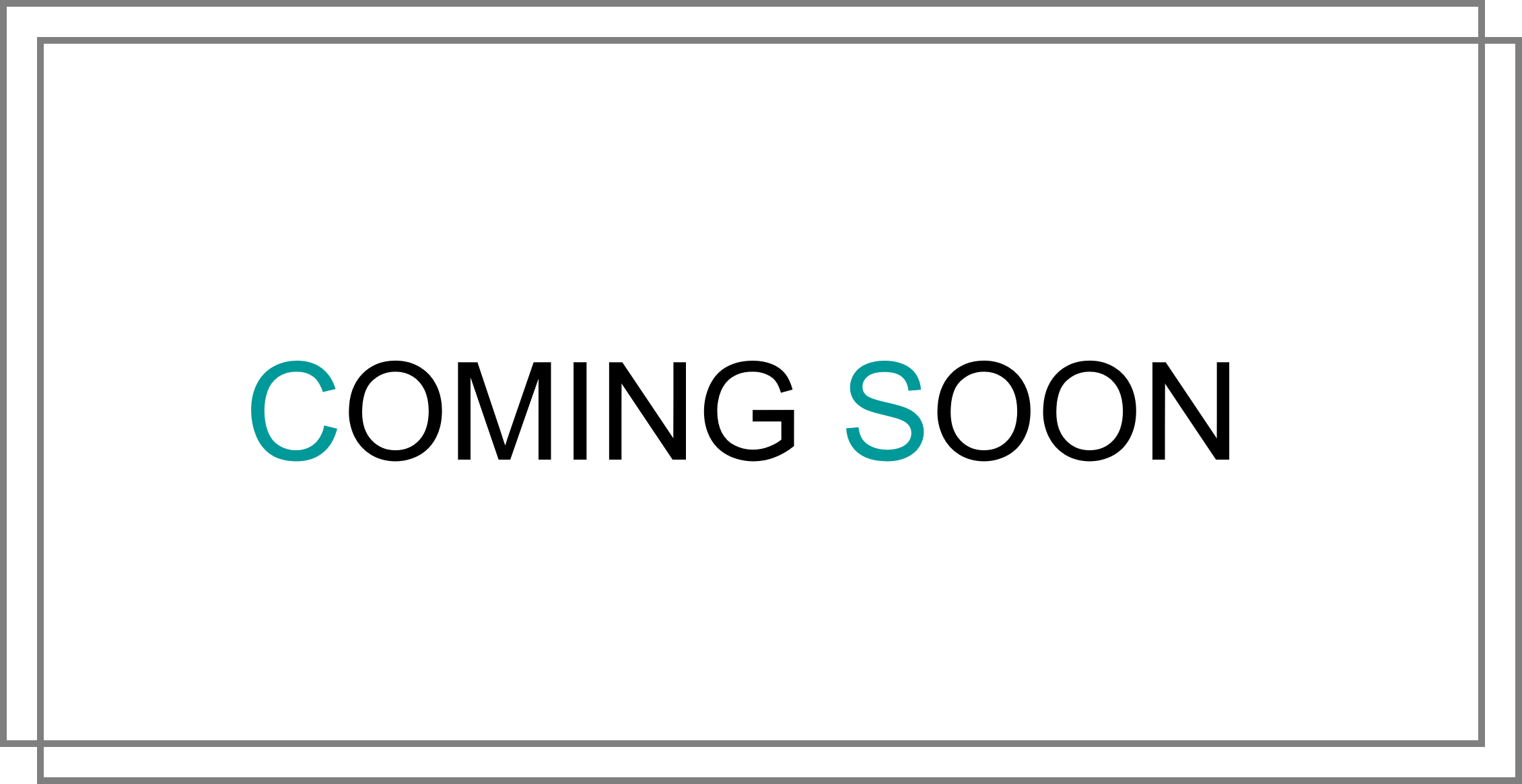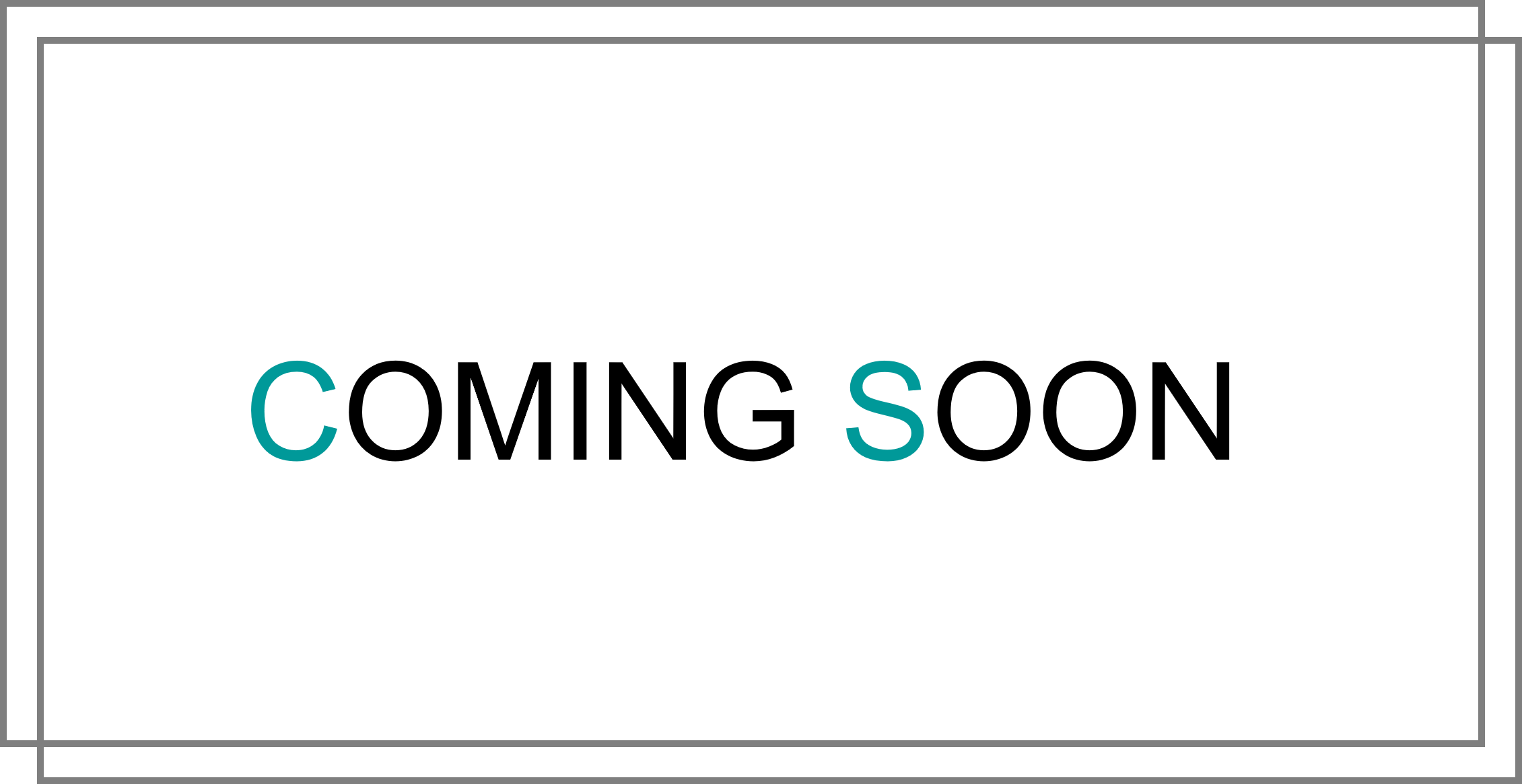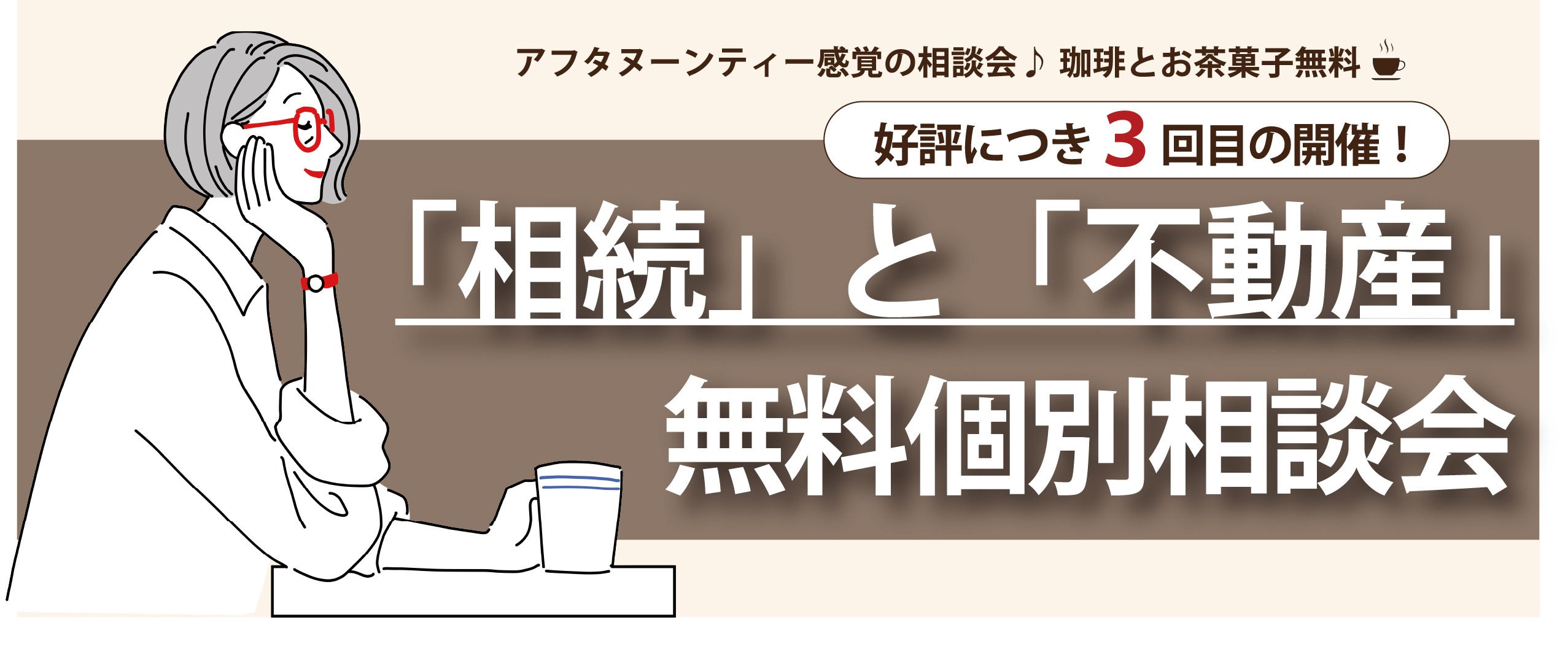夏本番を迎える7月、日本の古典的な呼び名では「文月(ふみづき)」といいます。
この名前には、短冊に願いを託す七夕や、書をしたためる文化、季節の祈りが込められています。
今回は、文月の由来とともに、日本らしい季節感、行事、風物詩、暮らしの知恵までを紐解いていきます。
1. 文月とは?7月の和風月名の意味と由来
「文」を読む月という説
文月の「文(ふみ)」は「手紙」や「詩歌」を意味し、文をしたためる季節という説があります。
これは、七夕に短冊へ願いを書く風習から来ているとも言われます。
昔の人々はこの季節、思いを言葉にし、文字に込めて祈りを届けようとしていたのです。
稲の穂にちなむ別の由来も
別説として、「穂含月(ほふみづき)」が転じたとする説もあります。
これは、稲が穂を含み始める季節であることに由来するものです。
日本人の生活が自然と共にあったことを象徴する名前ともいえるでしょう。
2. 文月と旧暦・新暦の違い
旧暦の文月は今の8月
旧暦では文月は現在の8月頃にあたります。
つまり、稲穂が膨らみ始め、秋の気配が感じられる季節でした。
新暦の7月は梅雨明け直後で、やや時期にずれがある点も日本の季節文化の特徴です。
七夕と旧暦のズレ
現在は7月7日に行われる七夕も、旧暦では8月初旬の星の美しい時期に行われていました。
そのため、本来の風情や天体観測の意図を味わいたい方は、旧暦にあわせて楽しむのもおすすめです。
3. 文月と七夕:願いを託す夜の物語
織姫と彦星の伝説
七夕は、中国の「乞巧奠(きこうでん)」が奈良時代に日本へ伝わったもの。
織姫と彦星が年に一度、天の川で出会うというロマンティックな伝説は、短冊に願いを書く風習として定着しました。
五色の短冊と季節の祈り
笹に吊るされる五色の短冊には、健康・学問・家族円満など様々な願いが込められます。
色には意味があり、赤は礼、青は仁、黄は信、白は義、黒は智を表します。
子どもだけでなく、大人も祈りを言葉にする貴重な機会です。
4. 文月の自然と風物詩
蝉の声と夏空の音風景
梅雨明けとともに始まる蝉の大合唱は、まさに文月の風物詩。
アブラゼミやミンミンゼミの鳴き声は、真夏の訪れを告げる「音の風景」として日本人の心に深く刻まれています。
花火と夕涼みの文化
夜空を彩る花火大会が各地で開催されるのも文月の特徴。
浴衣をまとい、風鈴の音を聞きながら夕涼みを楽しむ日本の夏の情景は、風物詩そのものです。
これらの体験は、五感で季節を楽しむ日本文化の真髄といえます。
5. 文月の味覚と暮らしの知恵
旬の味:鰻、とうもろこし、枝豆
土用の丑の日には鰻を食べて暑気払いをする風習があります。
他にも、とうもろこし、枝豆、スイカなど、水分と栄養を補う夏の恵みが豊富です。
夏の旬を味わう:うな重
夏の旬を味わう:枝豆
七夕そうめんの由来
七夕にそうめんを食べるのは、中国の伝説に由来し、織姫が機織りで紡いだ糸に見立てたとも言われます。
涼しげで喉越しの良いそうめんは、暑い文月にぴったりの食文化です。
6. 暮らしに取り入れる文月の心
手紙を書く、願いを言葉にする
スマートフォンの時代だからこそ、あえて手紙を書く、願いを短冊に書く。
言葉を丁寧に紡ぐことは、自分の心と向き合う大切な時間になります。
涼しさを演出する工夫
簾や風鈴、打ち水など、夏を快適に過ごす日本独自の工夫も暮らしに取り入れてみましょう。
五感で涼を感じる「日本の涼」は、体だけでなく心も軽やかにしてくれます。
星に願いを込める、真夏の日本風景
笹飾りと七夕まつり
商店街や保育園、神社などに飾られる色とりどりの短冊。揺れる笹の葉に、人々の願いが静かに揺れています。
仙台七夕祭り
湘南ひらつか七夕まつりの笹飾り
夜空を彩る大輪の花火
日本各地で行われる花火大会の風景。浴衣姿で集まる人々と、打ち上がる大輪の花のコントラストは、日本の夏の象徴です。
東京お台場の花火
宮島水中花火大会
風鈴の音と蝉の声
縁側に吊るされた風鈴が、そよ風とともに涼やかな音を響かせる一方で、蝉の声が力強く夏を彩ります。
自然の音が重なり合う、夏らしい音風景が広がります。
夏の風鈴と簾
川越氷川神社の風鈴