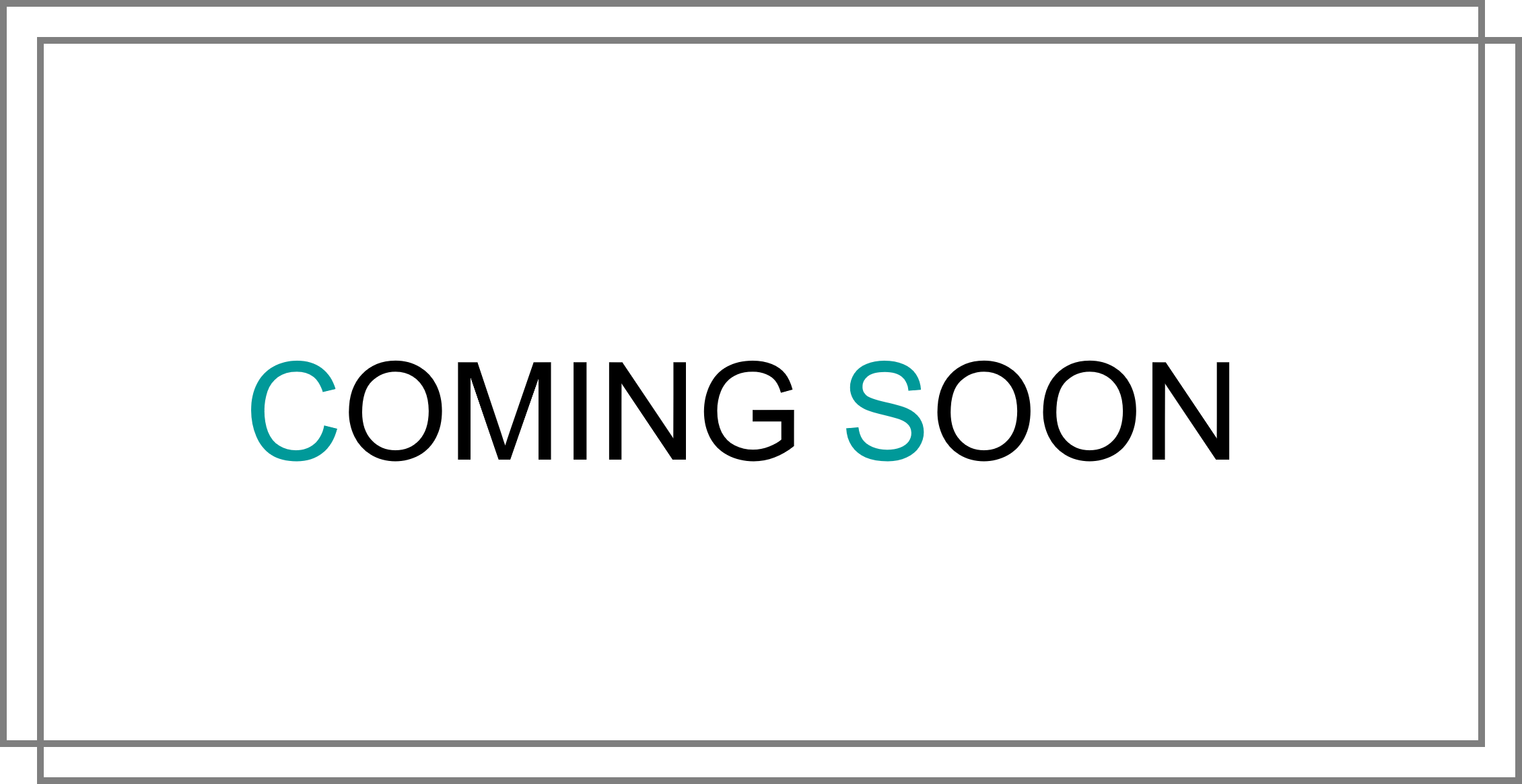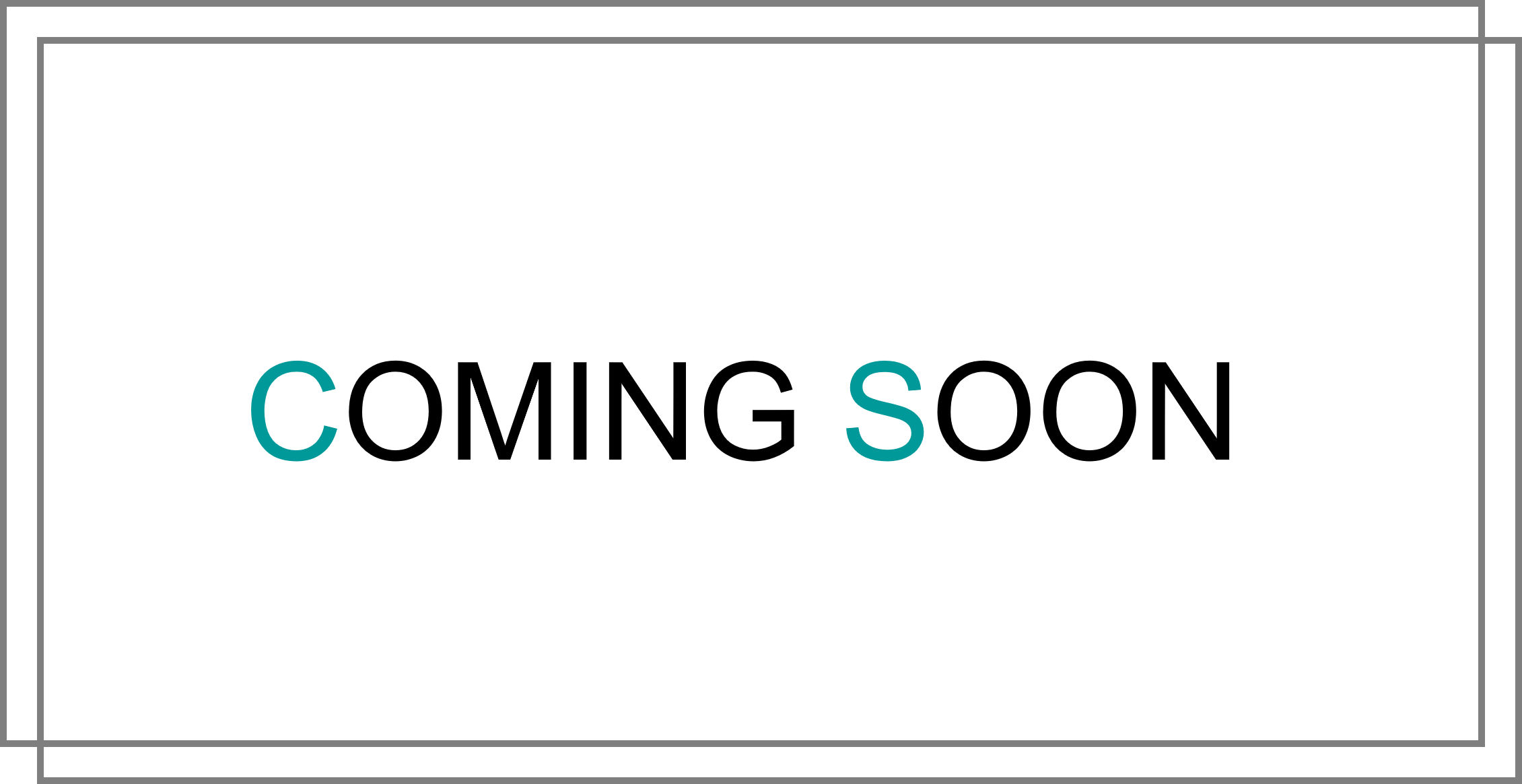11月、日本列島は秋から冬へと移り変わる節目の季節を迎えます。この月は和風月名で「霜月(しもつき)」と呼ばれ、朝夕の冷え込みや木々の葉が舞い落ちる様子からも、季節の変化を肌で感じることができます。
この記事では、「霜月」という言葉に込められた意味や歴史、自然の風物詩、文化との関わりを通じて、日本の11月の美しさを丁寧に紐解きます。
1. 霜月とは?11月の和風月名の意味と由来
「霜が降る月」という自然の気配
「霜月」は文字通り、「霜(しも)」が降り始める月を意味します。朝晩の冷え込みが厳しくなり、地面や草木に霜が降りることで、冬の訪れを感じさせる季節です。
日本人は昔から、こうした自然の変化に名前を与え、日々の暮らしに季節感を取り入れてきました。
旧暦では冬の始まり
旧暦の霜月は現在の12月頃にあたり、より冬らしさが際立つ時期でした。現代の新暦では11月に位置しますが、紅葉が終盤を迎え、朝霧や霜の光景も見られるなど、秋から冬への橋渡しのような趣があります。
2. 霜月と旧暦・新暦の違い
旧暦の「霜月」は年末の風情
旧暦では霜月は1年の終盤、冬の本格的な始まりとして捉えられていました。田畑の作業が一段落し、冬支度が始まる時期として、地域の暮らしにも変化が生まれます。
現在の11月もまた、自然が冬に向かう様子を私たちに伝えてくれます。
新暦11月の霜月が持つ現代的な季節感
現代の11月は、秋の終わりと冬の入り口という二面性を持っています。紅葉の見頃が続く地域もあれば、すでに木々が葉を落とし、冬の景色が始まる地域も。
霜月という呼び名は、まさにこの移ろう季節を象徴していると言えるでしょう。
3. 霜月の自然と風物詩
紅葉の終盤と落葉の風景
11月は、紅葉が見頃のピークを迎え、徐々に落葉へと移っていきます。公園や街路樹の落ち葉が地面を彩り、秋の余韻と冬の静けさが交錯する風景が広がります。
朝霜と冬の気配
早朝の草木に降りた霜が朝日を受けて輝く様子は、この季節ならではの美しさです。こうした自然の表情を観察することで、霜月の名前に込められた意味をより身近に感じられるでしょう。
冬の朝、窓辺の風景
雪に覆われた地面にきらめく霜と氷の結晶
4. 霜月にまつわる行事と文化
七五三と成長を祝う文化
11月15日は、日本の伝統行事「七五三」が行われる日です。3歳・5歳・7歳の子どもたちが晴れ着に身を包み、神社に参拝して成長を祝います。
この行事は、霜月という季節がもたらす神聖さや区切りの意識とも深くつながっています。
炉開きと茶の湯の季節
茶道の世界では11月は「炉開き」の季節。夏の間に使われていた風炉から、冬用の炉へと切り替える節目の行事です。
冬の静けさの中で行われる茶会は、霜月のしっとりとした季節感と調和し、心を落ち着ける時間をもたらしてくれます。
5. 暮らしの中で感じる霜月の風情
衣替えと冬支度
朝晩の冷え込みに合わせて、冬物のコートやマフラーが活躍する時期です。暖房器具を出したり、寝具を冬仕様に変えたりと、霜月は本格的な冬への準備を始める月でもあります。
旬の味覚と温かい料理
霜月には、里芋や大根、白菜といった冬野菜が旬を迎えます。鍋物や煮物など、体を内側から温める料理が恋しくなる時期でもあります。
霜月の味覚を取り入れることで、日々の食卓にも季節の移ろいを感じることができます。
冬野菜:大根
冬野菜:里芋
霜月の風情を映す自然と行事
落ち葉の絨毯と晩秋の陽射し
黄金色に染まったイチョウやカエデが落葉し、地面に敷き詰められたような風景が晩秋を感じさせます。

七五三の晴れ姿と神社の景色
晴れ着に身を包んだ子どもたちと、朱塗りの鳥居や紅葉が織りなす風景は、日本の季節の美を象徴する一枚です。

霜の降りた草花と朝の光
霜が降りた草花が朝日を受けてきらめく様子は、霜月ならではの静謐で幻想的な光景です。