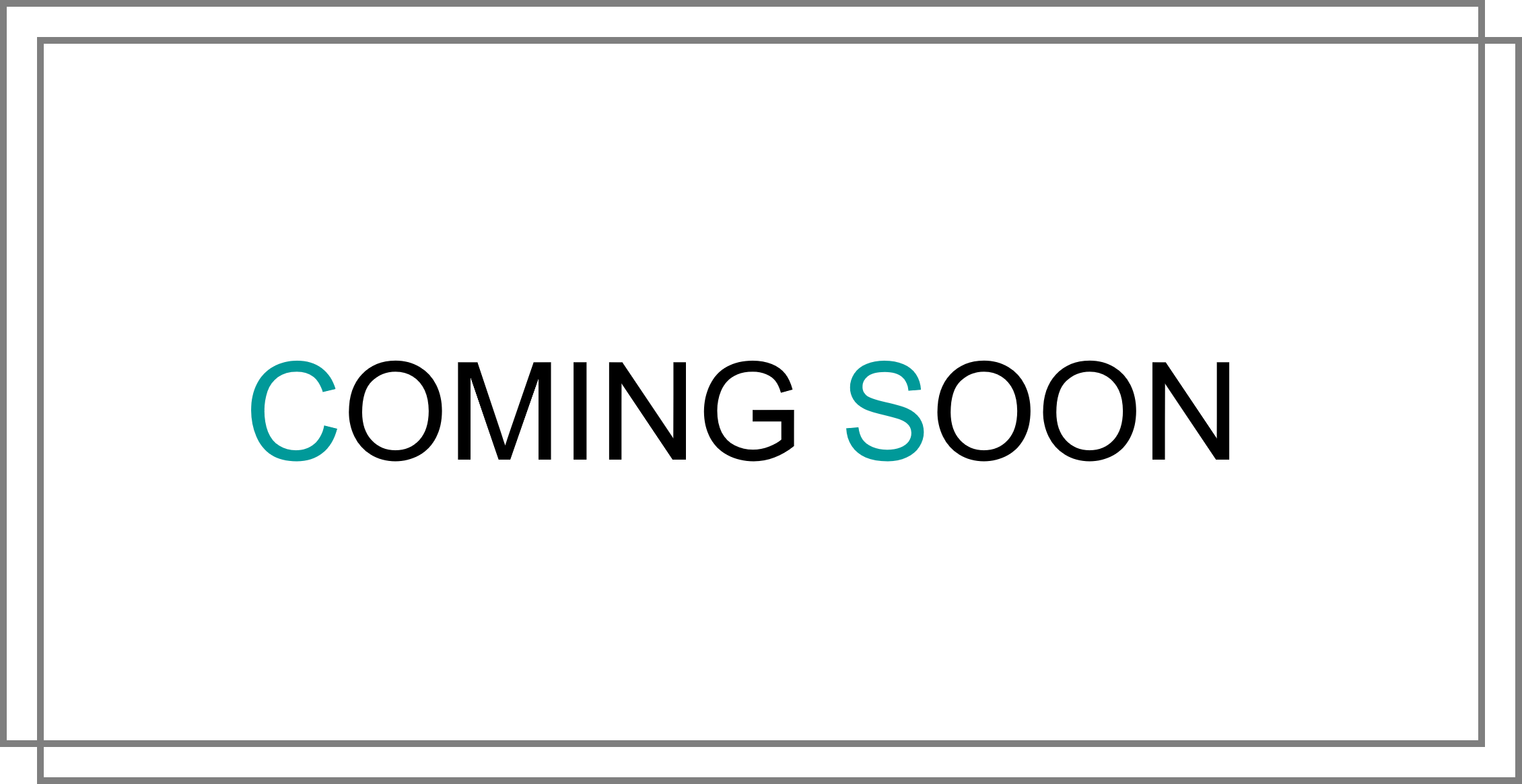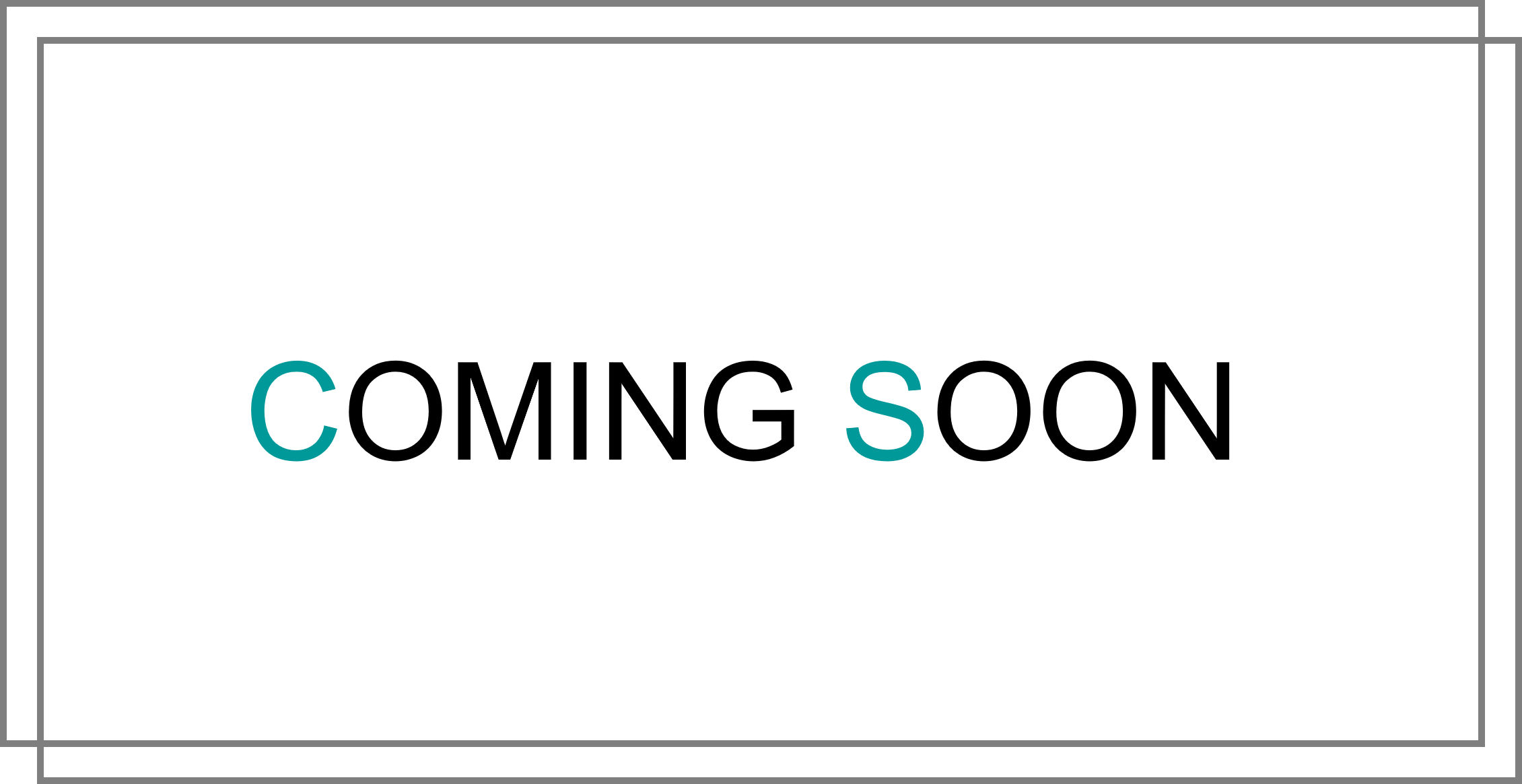身近な和紙といえば、障子や提灯、書道用の半紙などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
その源流は約1400年前。中国から製紙技術が伝わったことをきっかけに、日本独自の発展を遂げてきました。2014年には、手漉き和紙の技術がユネスコ無形文化遺産にも登録されています。長い時を紡ぎながら受け継がれてきた和紙の魅力と歴史を、ここからひもといてみましょう。
【和紙の歴史】
紙の伝来と日本での発展
紙の起源は、中国の後漢時代にさかのぼります。西暦105年頃、宦官の蔡倫(さいりん)が樹皮や麻くずなどを原料に紙を発明したと伝えられています。この技術はのちに朝鮮半島を経由して日本へ伝わり、『日本書紀』には西暦610年、百済の僧・曇徴(どんちょう)が製紙と墨の技術をもたらしたと記されています。
当初の紙は、主に貴族や寺院で経典の写経や公文書に用いられる貴重な素材でした。奈良時代には国家的な事業として製紙が行われ、「美濃紙」「豊前紙」「但馬紙」などが代表的な和紙として知られています。正倉院に残る古文書の多くもこれらの和紙で書かれたもので、千年以上を経た今なおほとんど劣化していないという事実は、和紙の優れた耐久性を雄弁に語っています。
中世から近世へ──地域ごとの発展
鎌倉時代に武士階級が台頭すると、文書の需要が一気に高まり、各地で和紙づくりが盛んになりました。とくに、楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)といった原料の栽培に適した地域では、土地ごとの特色を持つ紙が生まれていきます。
室町から江戸時代にかけては、和紙は庶民の生活にも浸透し、書物や浮世絵、襖紙、提灯、凧など、さまざまな用途に活用されるようになりました。
江戸時代には全国に紙の産地が形成され、「美濃紙」「越前奉書」「土佐和紙」「石州半紙」などが名を知られるようになります。これらの伝統は今日まで受け継がれ、なかでも「本美濃紙」「石州半紙」「細川紙」の三つは、2014年にユネスコ無形文化遺産として登録されました。
和紙で作られた手作りの箸置きと箸袋
和紙の提灯
【和紙の特徴】
強靭さと柔軟性
和紙の最大の特徴は、その「強さ」にあります。薄くても驚くほど丈夫で、折り曲げや引っ張りにも強いのは、原料となる植物の長い繊維をそのまま活かしているからです。
たとえば楮の繊維は約10ミリ前後と長く、洋紙の原料である木材パルプ(2〜3ミリ)に比べても圧倒的に長いことが分かります。これらの繊維が複雑に絡み合うことで紙が構成されるため、軽くても裂けにくく、破れても繊維同士が粘り強くつながっています。
自然な風合いと透け感
和紙には独特の光沢や温かみがあります。原料の種類や漉き方によって質感は異なり、たとえば三椏を使った紙は滑らかで繊細、楮はしなやかで強靭、雁皮は光沢があり薄くて上品です。
また、和紙特有の「透け感」や「繊維の揺らぎ」は、日本人の美意識に通じる“余白”や“陰影”の美を感じさせます。
吸湿性・通気性
和紙は空気をよく通し、湿気を吸収・放出する性質を持っています。これは日本の高温多湿な気候に非常に適しており、障子や襖などに用いられる理由の一つでもあります。室内の湿度を自然に調整し、光を柔らかく拡散することで快適な空間を生み出します。
保存性と修復性
和紙は酸を含まない中性素材であるため、劣化が遅く、長期保存に向いています。古文書や絵画の修復にも使用されており、世界中の博物館で“Japanese paper”として高く評価されています。西洋の古書修復でも和紙が欠かせない存在です。
【洋紙との違い】
和紙と洋紙の大きな違いは、「原料」と「製法」にあります。
洋紙は産業革命以降に発展した大量生産の紙であり、印刷や出版、事務用途には欠かせません。一方、和紙は職人の手による小規模生産が中心であり、その質感や強度、美しさは量産品にはない魅力を放ちます。どちらが優れているというよりも、「用途や目的の違い」によって使い分けられてきたのです。
【和紙の原料】
和紙の原料には、主に楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)の三種が用いられます。それぞれの性質と特徴を見てみましょう。
1. 楮(こうぞ)
クワ科の落葉低木で、最も一般的な和紙の原料です。繊維が長くて強いため、書道用紙、障子紙、版画用紙など幅広く使われています。紙にすると丈夫で腰があり、ややざらついた風合いが特徴です。寒冷地から温暖地まで栽培可能で、日本全国に分布しています。
2. 三椏(みつまた)
ジンチョウゲ科の植物で、枝が三つに分かれることからその名がつきました。繊維が細く短いため、表面が滑らかで上品な仕上がりになります。主に高級和紙や紙幣の原料として用いられており、日本の紙幣(日本銀行券)にも三椏が使われています。
3. 雁皮(がんぴ)
同じくジンチョウゲ科の植物で、自然生育が多く、栽培が難しいため希少です。繊維が非常に細かく光沢があり、薄くても強度があります。公文書や高級書画用紙、修復紙などに用いられます。耐久性と透明感が高く、“最高級の和紙原料”とされています。
和紙の原料
美濃紙
【和紙の製作工程】
伝統的な和紙づくりは、自然と向き合う手仕事です。ここでは代表的な手漉き和紙の工程を紹介します。
① 原料の収穫と蒸し
秋から冬にかけて、楮や三椏などの原料を収穫します。蒸して皮をはぎ、外皮・黒皮を取り除いて白皮(紙の原料部分)を得ます。
② 皮の処理
白皮を水にさらして汚れを落としたあと、灰汁やソーダ灰を加えた釜で煮て、繊維を柔らかくします。煮過ぎると繊維が切れてしまうため、火加減や時間の見極めが重要です。
③ 不純物の除去(塵取り)
煮た繊維を冷水にさらし、一枚一枚手で異物を取り除きます。この作業は非常に根気のいる工程で、紙の仕上がりを左右します。
④ 打解(だかい)・叩解(こうかい)
不純物を取り除いた繊維を棒などで叩き、繊維をほぐして水中に均等に分散できる状態にします。
⑤ 紙漉き
大きな木枠(簀桁=すげた)を使い、水の中で繊維を揺らして絡ませながら薄く広げます。
ここで使われるのが「ねり」と呼ばれる粘液(トロロアオイの根から取れる植物粘剤)です。ねりを加えることで繊維が水中に均等に分散し、紙を均一に漉くことができます。
和紙の伝統技法には「流し漉き」「溜め漉き」があり、前者は繊維を流動させながら層を重ね、より強靭な紙をつくります。
⑥ 圧搾・乾燥
漉き上げた紙を重ねて水を絞り、板や金属板に貼って天日で乾燥させます。
日光と風を利用した自然乾燥は、紙に自然な白さと張りを与えます。機械乾燥と違い、和紙特有のしなやかさが生まれるのです。
⑦ 仕上げ
乾いた紙を一枚ずつはがし、選別・仕上げを行います。用途によっては染色や加工を施すこともあります。
紙漉き
紙漉き
(まとめ)
和紙の需要は時代の変化に合わせて減少した時期もありましたが、近年ではその価値が再評価されています。
たとえば、照明デザインや建築内装、ファッション、アート作品、文房具など、現代の感性と融合した使われ方が広がっています。
また、和紙の持つ環境負荷の低さやリサイクル性も注目されており、サステナブルな素材としての期待も高まっています。
さらに、文化財修復やデジタル保存の分野でも、和紙の「呼吸する紙」としての特性が生かされています。海外の美術館では、劣化した絵画や古書の補修に日本産の和紙を使うことが一般的になっています。
伝統を守りながらも新しい表現や用途へと広がる和紙は、現代の暮らしや文化において、いまなお重要な存在であり続けています。