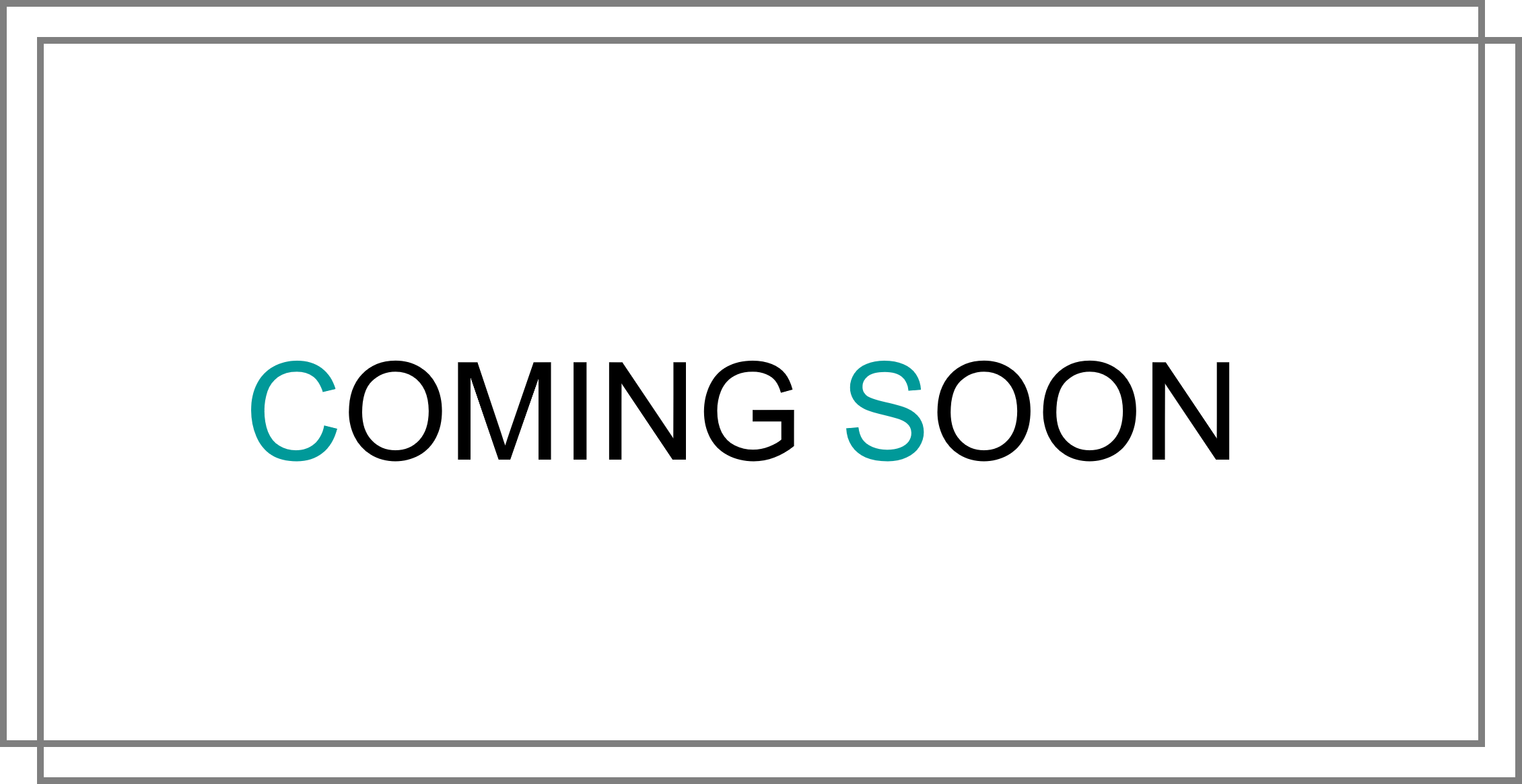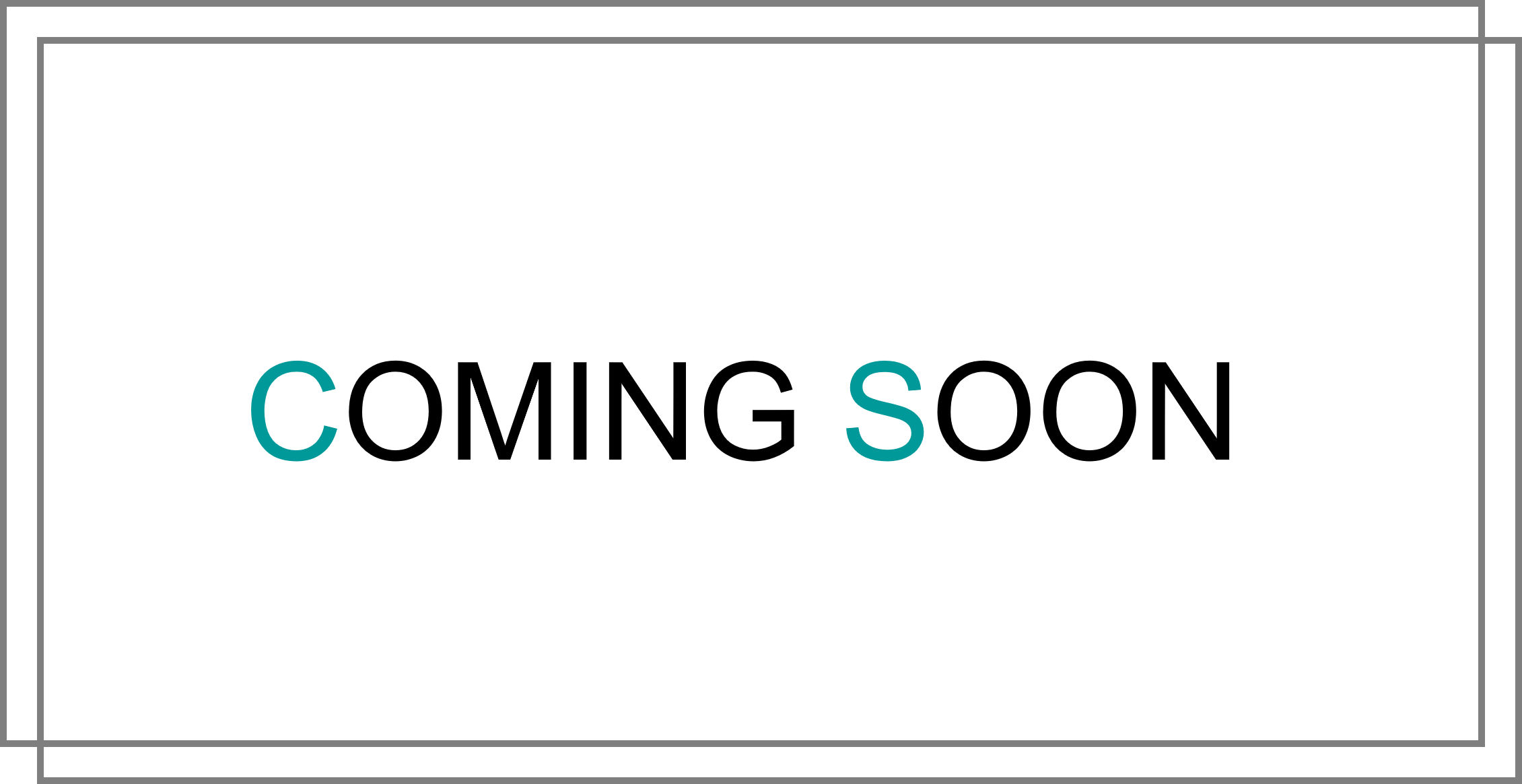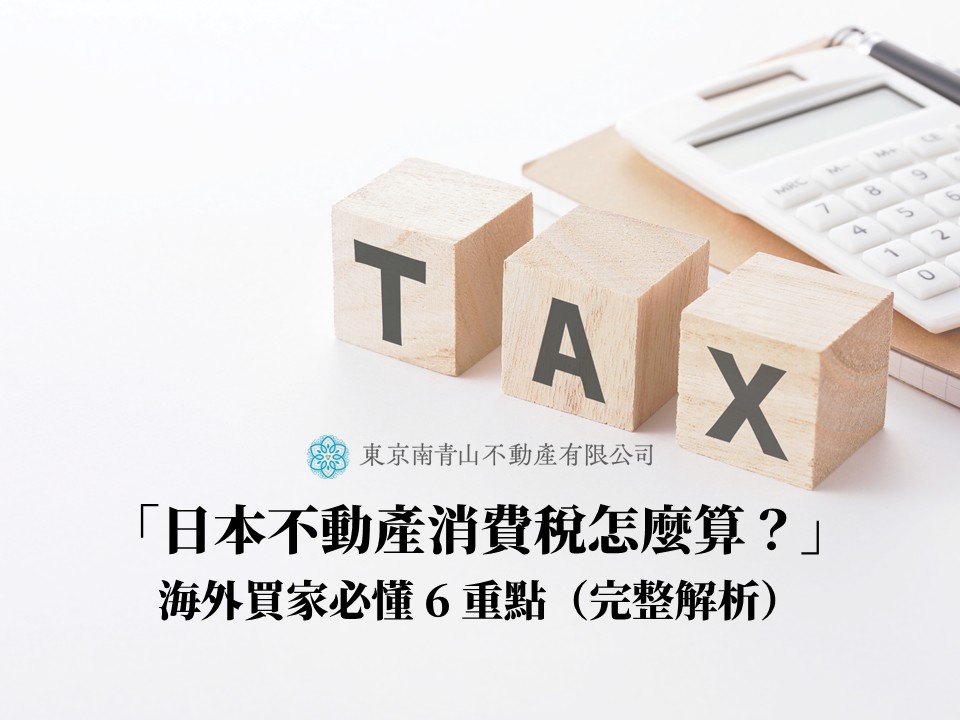紫陽花が咲き、しとしとと雨が降る6月。
この時期、日本では「水無月(みなづき)」という和風月名が使われてきました。
梅雨の時期でありながら「水が無い」と書く、この不思議な名前の由来や、季節の風景、行事、暮らしの知恵まで、初夏の日本文化を味わってみましょう。

紫陽花
1. 水無月とは?6月の和風月名の意味と由来
「水無月」の「無」は“ない”ではない?
「水無月」とは旧暦6月を指す和風月名で、「みなづき」と読みます。
一見「水が無い月」のように見えますが、「無」は「の」にあたる連体助詞とされ、「水の月」という意味を持ちます。
つまり、水が不足する月ではなく、「田に水を張る月」、すなわち田植えの水をたたえた時期を意味しているのです。
梅雨と重なる季節感
旧暦では夏真っ盛りの月
現在の新暦6月は梅雨の最中にあたります。
雨が降り続くこの時期に「水が無い」と表現するのは不思議ですが、旧暦では夏本番の7月中旬ごろに相当し、乾いた土地に水を引く時期だったと考えられています。
言葉の由来には、季節と農業の密接な関係が見て取れます。
2. 水無月と旧暦・新暦の違
旧暦の6月は、新暦では7月上旬〜中旬にあたるため、水不足や暑さが本格化する季節でした。
現代の6月のイメージと比べて、時期がややずれていることを理解することで、「水無月」の本来の意味がより深く見えてきます。
水と暮らす日本の知恵
水が多すぎても、少なすぎても困る——そんな日本の自然と向き合ってきた歴史が、水無月という名に凝縮されています。
水を制し、水を敬い、水とともに暮らす。その意識は、現代の防災・環境にも通じる文化的教訓です。
3. 水無月の文学と神事に見る「祓い」のこころ
万葉集に詠まれた雨の情景
万葉集では、「五月雨(さみだれ)」や「みなづき」に関する和歌が多く詠まれています。
雨の続く日々の中に、自然への祈りや恵みへの感謝が込められています。
じめじめとした空気のなかにも、美しい風情が見出されていました。
夏越の祓と茅の輪くぐり
6月の末日には「夏越の祓(なごしのはらえ)」という神事が各地の神社で行われます。
茅(ち)の輪をくぐることで、半年間の穢れを清め、残り半年の無病息災を祈ります。
これは水無月の精神を象徴する行事ともいえるでしょう。
夏越の祓と茅の輪くぐり
茅の輪くぐり
4. 水無月の自然と風物詩
紫陽花と雨の美
水無月の代表的な花といえば、やはり紫陽花(あじさい)。
雨粒をまといながら色を変えていく紫陽花の姿は、移ろいゆく日本の季節感そのものです。
寺社や庭園での「紫陽花まつり」も各地で開催され、梅雨の楽しみとなっています。
紫陽花
紫陽花
蛍が灯す初夏の夜
6月中旬からは、蛍が舞う幻想的な風景も見られます。
水辺に生息するホタルは、水の豊かさと自然環境のバロメーターでもあります。
都市部でも見られるスポットがあり、雨上がりの夜は観察に最適なタイミングです。
蛍
蛍
5. 水無月の味覚と季節行事
和菓子「水無月」をいただく
6月30日に食べる和菓子「水無月」は、白いういろうの上に小豆をのせた三角形のお菓子。
京都発祥で、夏越の祓の日に邪気払いの意味を込めて食べられます。
三角形は氷をかたどり、小豆には厄除けの意味があります。
和菓子:水無月
和菓子:水無月
梅、青じそ、初夏の保存食
梅仕事が始まるのもこの季節。梅干しや梅酒を漬けたり、青じそやラッキョウで常備菜を作ったりと、保存食作りにぴったりの時期です。
梅雨の湿気に対抗する、昔ながらの暮らしの知恵です。
梅仕事
梅仕事:梅酒や梅ジュースを漬ける
6. 暮らしに取り入れる水無月のこころ
涼と清めを暮らしに
玄関に茅の輪飾りを置いたり、雨の日にお気に入りの傘で外に出かけたり、
心も空間も「祓う・整える」ことが水無月の楽しみ方。
香りのよい和アロマやお香も、湿気対策と気分転換におすすめです
季節の移ろいをゆったり味わ
雨音に耳を澄ませ、紫陽花を眺め、湯気立つ湯呑みに初夏の香りを添える——
そんなゆったりとした時間が、梅雨を味方につける鍵になります。
7. まとめ|水無月が映し出す、祈りと浄化の季節
水無月は、自然とともに暮らす日本人の知恵や感性がぎゅっと詰まった季節。
名前に込められた意味、雨の美しさ、伝統行事や味覚……
すべてが静かに「新たな半年へ」の祈りを込めています。
静かに、自分と自然を整える——
水無月はそんな“心の手入れ”の月なのかもしれません。
●写真で紹介する日本の6月:雨と緑が生む、6月の日本風景 (注釈)紫陽花と雨に濡れる石畳
濡れた石畳と紫陽花
Happy Father's Day
さくらんぼ