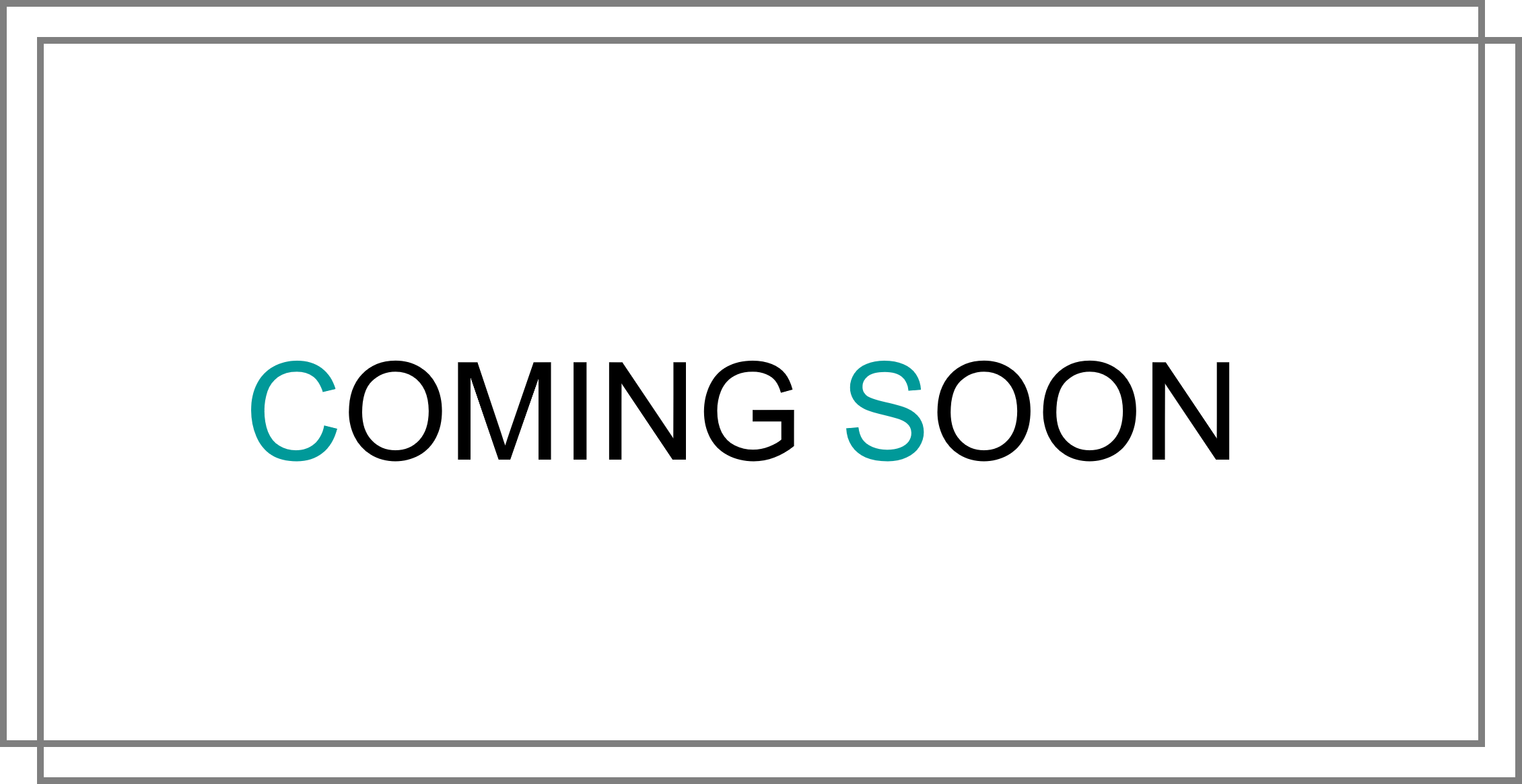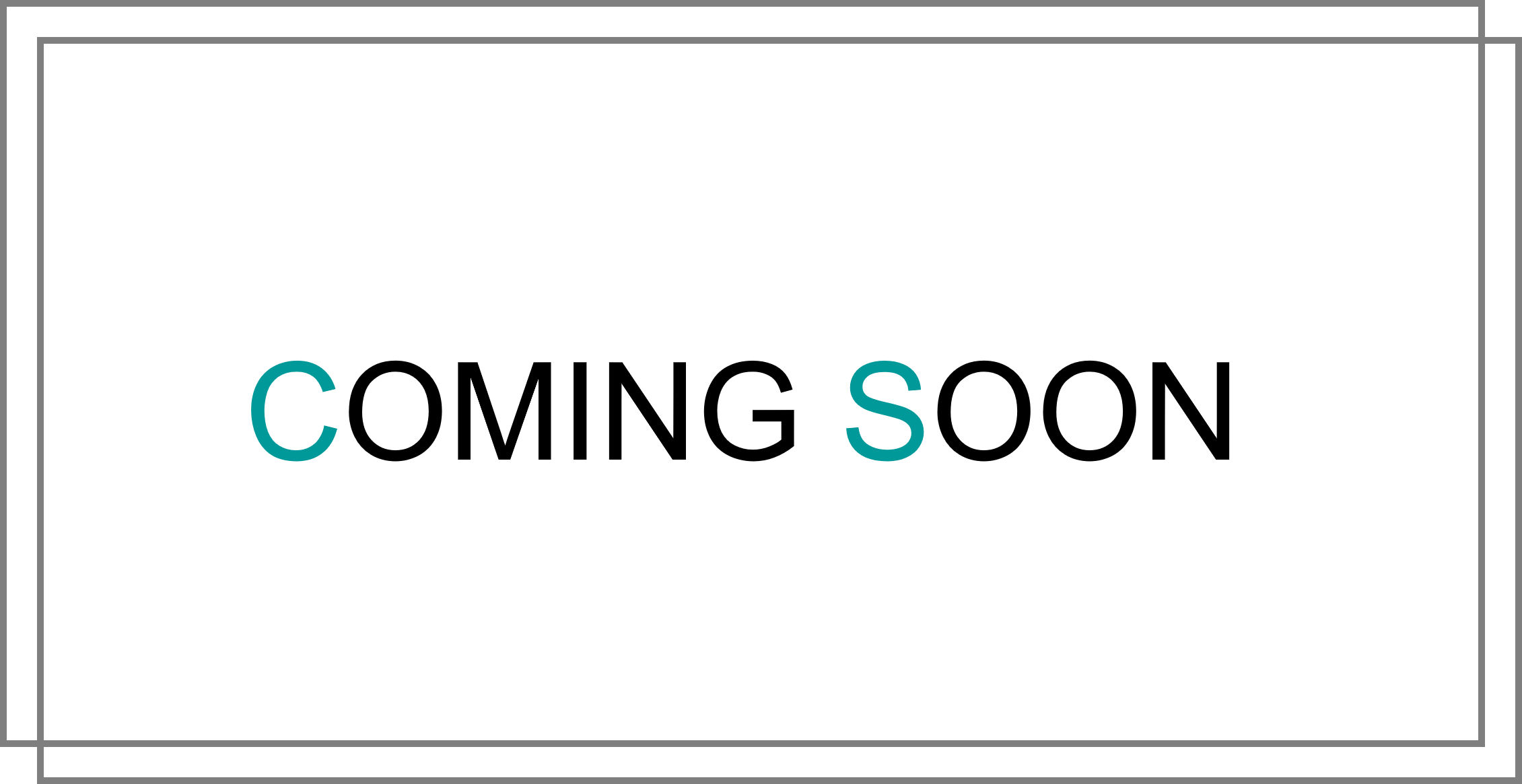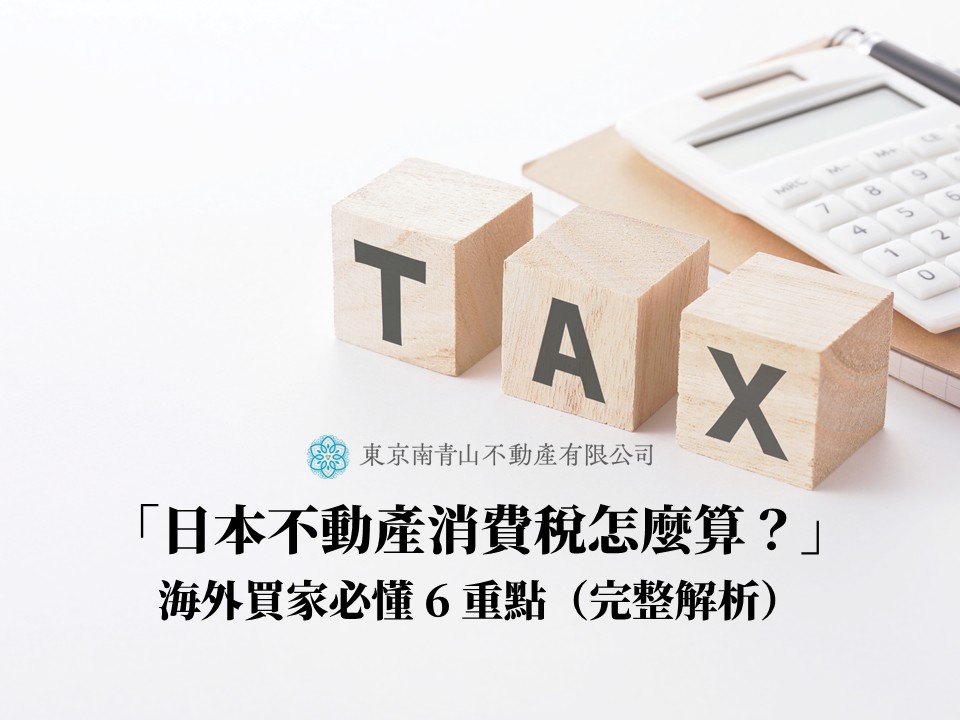さまざまな植物を組み合わせて花器に生け、愛でて楽しむ「いけばな」。「華道」や「花道」、「生け花」、「活花」、「挿花」などと記されるように、四季折々の草花を用いるのが大きな特徴です。
いけばなが発展したのは、室町時代。今回は日本で育まれたいけばなの文化についてご紹介します。
祭壇に供える「供花」から発展
いけばなの発祥についてはほとんどわかっておらず、一説によると、中国から仏教が伝来した際に伝わった、祭壇に供える花「供花(くげ)」の慣習からはじまったと考えられています。
現在のように花器に草花を生けるスタイルが生まれたのは室町時代。中国から絵画や陶磁器、書跡など「唐物(からもの)」と呼ばれるさまざまな美術品がもたらされ、現代の日本家屋の原型となった住宅様式「書院造」の成立により、床の間に花や掛け軸、茶香炉などを飾る文化が生まれました。この頃に誕生した、いけばなの最も古い様式が「立て花(たてばな)」です。立て花では花器の中心に「真(しん)」と呼ばれる枝を直立させ、その根元に「下草(したくさ)」として季節ごとの草花をあしらい、豊かな自然の風景を表現します。室町時代には、京都・六角堂の僧侶、池坊専慶(いけのぼう・せんけい)が花を生ける名手として文献に登場します。さらに時代が進むと、池坊専応(いけのぼう・せんおう)がいけばなの理論を『池坊専応口伝』としてまとめ、弟子たちに相伝するようになりました。
豪華絢爛な「立花」、精神性を追求した「抛入花」の成立
やがて立て花は客人をもてなす場の装飾として用いられるようになり、江戸時代前期には「立花(りっか)」として成立します。大型で豪華絢爛、ダイナミックな立花は、武家階級など富裕層から、やがて町人文化にも普及していきました。
一方、それと同時に、「抛入花(なげいればな)」の様式も生まれ、関心が高まっていました。立花と対照的に、小型で決まった様式がなく、自由に花を生ける抛入花は、生活に寄り添う花飾りとして盛んになり、江戸時代後期に入ると、抛入花を昇華させた「生花(しょうか)」として成立。現代のいけばなの礎となりました。
「生花」では1~3種類の植物を使って、草木のいきいきとした美しさを表現します。万物の基礎とされている三才、つまり天・地・人になぞらえ、「真(しん)」「副(そえ)」「体(たい)」の3つの役枝(やくし)で構成されるのが特徴で、それぞれの役枝には異なる役割があります。最も長い「真」は、作品の芯、主軸となる存在。そのため、初めに「真」を生け、「副」、「体」の順に生けていきます。上から見ると不等辺三角形になるように、手前から見ると奥側に「真」がくるように3つの役枝が配置されているのが理想とされています。
「いけばな」と「フラワーアレンジメント」の違い
ところで、同じく植物を使った芸術に「フラワーアレンジメント」があります。フラワーアレンジメントは地中海やヨーロッパで発生したと考えられている西洋発祥の文化。いけばなとフラワーアレンジメントでは道具(いけばなでは土台に剣山を、フラワーアレンジメントでは『オアシス』と呼ばれる給水スポンジを用いるなど)も異なりますが、最も大きな違いは、いけばなは“自然”を再現する、植物のありのままの姿を生かすことを大切にしているのに対し、フラワーアレンジメントは、“形”を作り込んで装飾する点にあります。
また、いけばなは、基本的に一方向(正面)から鑑賞することを前提につくられているのに対し、フラワーアレンジメントは、空間やテーブルの中央に配置されることも多いため、360度どこから見ても美しく見えるよう、デコラティブに装飾されているのも大きな違いです。さらに、いけばなが「間(ま)」や余白を活かし、象徴的に表現されているのに対し、フラワーアレンジメントは全体的にボリュームがあり、色彩も華やかで、装飾性が重視されている点も対照的。いけばなが“引き算の美学”なら、フラワーアレンジメントは“足し算の美学”といえるでしょう。それぞれに思想や目的、美意識が異なるため、同じ草花を用いてもまったく違った視点からその植物の美しさが表現され、それぞれに魅力があります。
現代のいけばなはより自由に、アーティスティックに進化
歴史の始まりには男性の教養の一環とされていたいけばなですが、明治から昭和時代にかけて女学校で教育課程に取り入れられるなど「花嫁修業」の一つとして重視されるようになりました。その結果、現在もいけばなを嗜む人口を紐解いてみると女性の方が多いようですが、性別や年齢を超えて楽しめる芸術です。
いけばなを学ぶことには、日々移ろう四季や自然と向き合うことで感性が磨かれる、集中力が養われる、美しい花を愛でることで心を落ち着ける、ストレスを和らげるなど、さまざまな効果があるといわれています。もともと、いけばながお客様をもてなす目的で発展したように、いつものお部屋に季節の花が生けられていることで空間の雰囲気が変わり、安らぎをもたらすことでしょう。
現在、三大流派と呼ばれる「池坊(いけのぼう)」「草月流(そうげつりゅう)」「小原流(おはらりゅう)をはじめ、さまざまな流派があり、多くの人々がいけばなを楽しんでいます。また、近年では、従来の「真・副・体」の構成にとらわれず、抽象的・彫刻的な作品、個性豊かなインスタレーションを手がけるアーティストも登場しています。
日々の暮らしを豊かに彩る「いけばな」の世界。ぜひ一度、体験教室や、いけばな展などに足を運んでその魅力に触れてみてください。