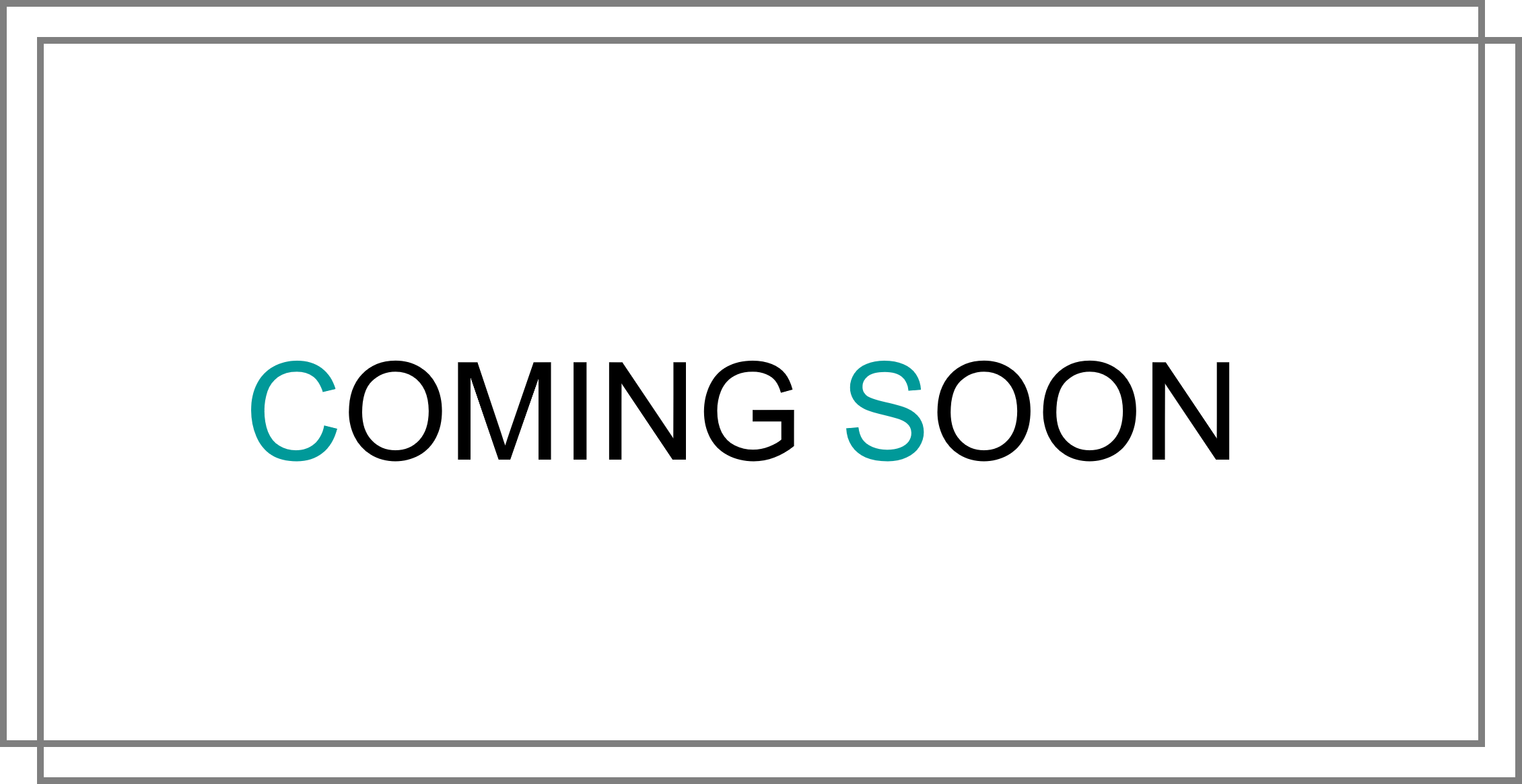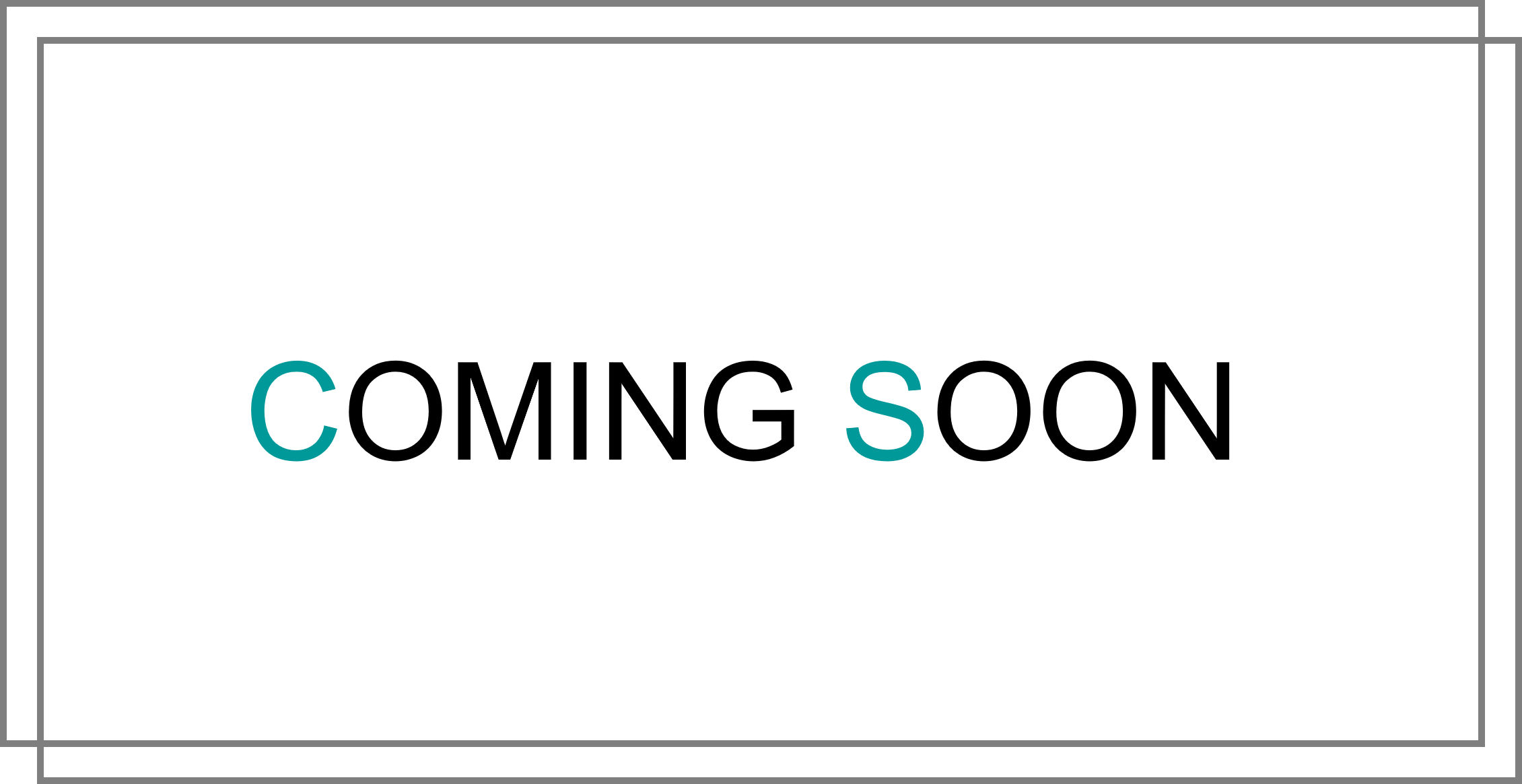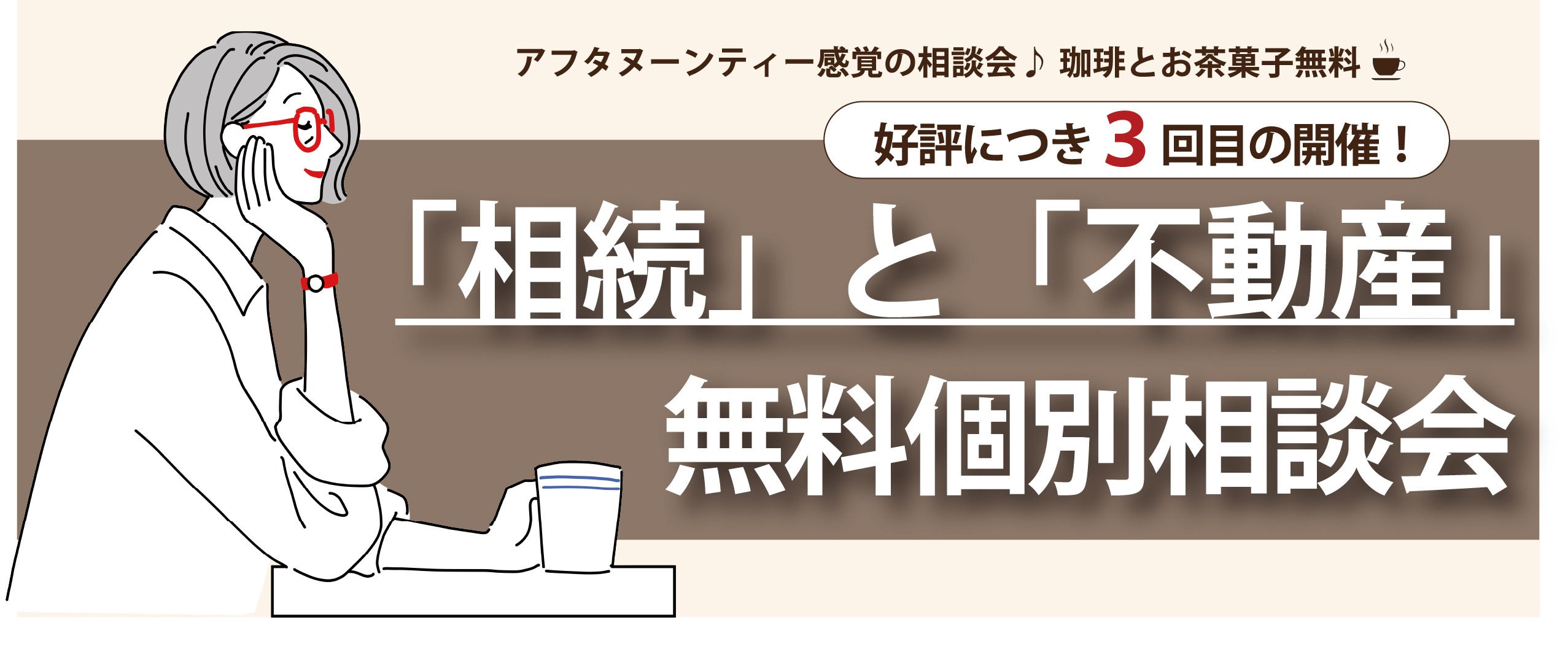真夏の暑さがピークを迎える8月。容赦ない陽射しと蝉しぐれの中にも、季節はゆっくりと秋へと向かっています。
この月の和風月名は「葉月(はづき)」。かつての旧暦では秋の入口を意味していましたが、現代の葉月は“盛夏の終盤”を思わせる季節でもあります。
1. 葉月とは?8月の和風月名の意味と由来
「葉が落ちる月」という説
「葉月」という言葉の語源には、「葉落ち月(はおちづき)」が転じたという説があります。旧暦では8月は今の9月中旬から10月初旬頃にあたり、紅葉の兆しや落葉が始まる季節とされていたのです。
このため、葉月は秋の訪れを示す自然現象の一つとして、名づけられたと考えられています。
葉が落ちる季節?現代とのずれ
旧暦の感覚とは異なり、現代の8月は連日の猛暑が続きます。落葉のイメージとはかけ離れていますが、空の色や風のわずかな変化、虫の音などに、次の季節の兆しを見つけるのは日本人ならではの感性です。
2. 葉月と旧暦・新暦の違い
旧暦では“秋の入口”
旧暦の葉月は現在の9月ごろにあたり、すでに秋風が吹き始める時期でした。したがって「葉が落ちる月」とされるのも自然なことです。
新暦との季節感のギャップ
現代の暦では8月は夏のピークと重なり、葉月という名と実際の気候の間にギャップがあります。その違いを知ることで、暦の歴史や文化への理解が深まります。
3. 葉月とお盆:先祖と向き合う日本の文化
お盆の行事と祖霊信仰
8月といえばお盆の季節。仏教と祖霊信仰が融合した日本独自の行事で、迎え火や送り火、提灯などを用いて祖先を迎え、感謝を捧げる風習が全国各地に伝わります。
家族のつながりと静けさ
家族が帰省し、故郷で静かに過ごす時間は、日本人の精神文化を象徴するものです。忙しい日常の中で、自分のルーツに立ち返るひとときでもあります。
4. 葉月の自然と風物詩
虫の音に秋の兆しを聴く
夜になると、鈴虫やコオロギの音色が聞こえてきます。昼の蝉とは違うその響きに、ふと秋の気配を感じることも。葉月は五感で季節の変化を味わえる時期です。
花火大会と送り火の夜
夏の風物詩・花火大会もこの時期にピークを迎えます。一方、お盆の送り火は静けさをまとい、対照的な情景を演出します。賑やかさと静寂の共存が、日本の夏らしさを際立たせます。
5. 葉月の味覚と季節の恵み
夏野菜とお盆の供え物
ナスやキュウリなどの夏野菜が旬を迎えるこの時期。精霊馬(しょうりょううま)として、キュウリを馬、ナスを牛に見立てて供える習慣は、野菜を通じて祖先とつながる日本文化の一面を物語ります。
食卓で感じる季節の変わり目
枝豆やトウモロコシといった夏の味覚に加え、早生の梨やぶどうなど、初秋の果物が市場に出回り始めます。食卓を通じて、葉月の季節感を味わうことができます。
キュウリの馬とナスの牛(精霊馬)
幸水梨
6. 暮らしに取り入れる葉月のこころ
涼を楽しむ知恵と工夫
風鈴の音や打ち水、すだれなど、日本には視覚や聴覚で“涼”を感じる暮らしの知恵があります。葉月は、自然の力を借りて心地よく過ごす工夫が輝く月でもあります。
自然との調和を意識する時間
猛暑の中でも、自然との調和を大切にする暮らし方は、心を落ち着けてくれます。虫の声に耳を傾けたり、夕暮れの空を眺めたりすることで、日常に穏やかな彩りを添えられます。
夏と秋が交差する、静と動の葉月風景
迎え火・送り火の幻想的な夜
玄関先に揺れる火の灯、提灯の淡い光。お盆の夜にしか現れない幻想的な風景が広がります。
花火大会に映える夏の夜空
夜空を彩る大輪の花火。日本の夏の締めくくりとして、多くの人が感動を胸に刻みます。
野菜の精霊馬と仏前の飾り
お盆の風習で用意される精霊馬や精霊牛。先祖を迎え、送るという行為を日常の道具で表現する日本人の精神文化が見えてきます。
お盆の迎え火・送り火
湖上の夜空を彩る壮大な花火